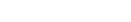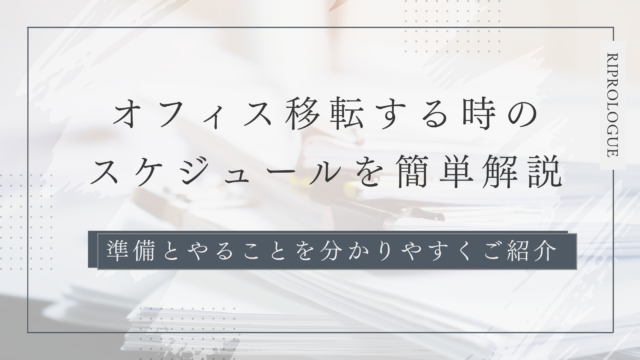働き方改革を推進するうえで、オフィス移転は柔軟な働き方や社員満足度を実現する重要なチャンスです。本記事では、フリーアドレスやコミュニケーションを促進する空間設計の工夫を中心に、移転を成功させるポイントと専門家への相談の重要性を解説します。

働き方改革とオフィス移転の関係とは?

働き方改革に必要な3つの要素
働き方改革を進めるには、制度・仕組み・空間の3つの要素から環境を整える必要があります。
- 制度設計:フレックス制やリモートワークなど、多様な働き方を選べるルールづくり
- ICT活用:クラウドツールやコミュニケーションアプリの導入・活用による業務効率化
- オフィス空間:集中と協働が両立するレイアウト、社員の心理に配慮したスペース設計
これらの要素が連携することで、働き方改革は単なるスローガンではなく、実行可能な変革へとつながります。
オフィス移転が改革推進のきっかけになる理由
オフィス移転は、働き方を見直す絶好の機会です。新しい空間に移ることで、業務の再構築や文化の刷新が促されるため、働き方改革の実行に勢いがつきます。
移転プロジェクトには経営層や人事、現場部門が関与するため、組織を横断した“共創”が生まれやすくなります。業務動線、コミュニケーション課題、部署間の物理的距離などを総点検できるタイミングは、実は移転時をおいて他にありません。
オフィス環境と社員意識の相関関係
オフィス環境は、社員の意識・行動に大きな影響を与えます。たとえば、閉鎖的なレイアウトでは発言が控えられ、開放的な空間では雑談からのアイデア創出が起こりやすくなります。
また、快適でストレスの少ない空間は、離職率の低下や業務集中度の向上にもつながります。オフィスは単なる仕事場ではなく、企業文化やチームワークを体現する「場」であるという意識が重要です。
空間設計で変わる社員の働き方と満足度
レイアウト変更がもたらす行動の変化
オフィスのレイアウトは、社員の行動様式に直接影響します。個人作業が中心の環境では、孤立しがちで連携が生まれにくく、反対にオープンなデスク配置では自然な会話が生まれやすくなります。
また、オフィス内の動線が複雑だと、ちょっとした移動にもストレスがたまります。通路の幅や通過ルートを見直すことで、業務効率だけでなく心理的負担も軽減されます。
行動に合わせた空間設計は、無駄な移動や業務の重複を減らし、生産性の向上にも寄与します。
フリーアドレスが与える心理的影響
フリーアドレスは物理的な自由度だけでなく、心理的な開放感や自律性にもつながります。個人の裁量で作業環境を選べることは、働きやすさや自立性の向上に直結します。一方で、居場所がないという不安を生まないようにする工夫も不可欠です。
以下のような取り組みが有効です。
- 自席に代わる“マイエリア”の設定(ロッカーや固定収納)
- 座席の事前予約システムによる混乱の回避
- 各自が落ち着ける環境を選べるゾーニングの導入
コミュニケーションを促進する配置設計
オフィス設計で注目されているのが、偶発的な会話や交流を促す配置の工夫です。たとえば、共用エリアやカフェスペースを通る導線にすることで、部署を超えたコミュニケーションが活性化されます。
加えて、部門の物理的な位置関係を変えるだけでも、横のつながりが強化され、情報共有や意思決定のスピードが上がります。
集中・雑談のバランスを取る工夫
働きやすいオフィスには、静けさと活気の“共存”が求められます。特定のエリアは個室ブースとして集中用に設け、他方で自由に会話できるリフレッシュエリアをつくることで、オンオフの切り替えがしやすくなります。この切り替えが可能な空間こそが、心地よい職場環境の鍵を握ります。
快適な採光・空調・音環境
社員が長く働きたいと感じるには、「居心地のよさ」が大きく影響します。採光・空調・音環境などへの配慮、家具の座り心地、色彩の調和といった細部へのこだわりが、快適性に直結します。
フリーアドレス導入の課題と対策
よくある失敗例とその原因
フリーアドレス導入にあたってよくある失敗は、計画段階での“目的不在”です。
以下のような問題が典型です。
- 席が確保できず不満が増加
- 必要な物品が周囲にない
- 誰がどこにいるか把握できず業務効率が低下
これらは、多くが事前のシミュレーション不足や運用ルールの曖昧さに起因します。
導入前に整理すべき社内ルール
フリーアドレスを円滑に運用するには、社内ルールの整備が不可欠です。
- 共有スペースでの私物管理ルールの明文化
- 清掃・片付けの習慣化を促すチェックリストの導入
- 出社率や席数に応じた予約・使用ガイドラインの明確化
こうした“あいまい”を排除する取り組みが、社内全体の納得感を高めます。
ITツールによる補完と運用の最適化
座席予約や社内在席確認ツールの導入は、フリーアドレスの機能性を支えます。加えて、オンラインでの資料共有やプロジェクト進捗管理ができるツールと連動させることで、離れていてもスムーズな連携が可能になります。
テクノロジーによって運用の煩雑さを減らし、定着率を高める設計が重要です。
定着のための組織マネジメント
制度やツールが整っても、文化として根付かなければ失敗に終わります。定着させるには、上司やチームリーダーが率先して実践し、社員同士でのノウハウ共有を促すことが鍵です。
現場主導の「使いやすい仕組み」にすることで、制度疲労を防ぎながら運用の質を高められます。

オフィス移転を成功に導くプロの支援とは
プロのレイアウト提案が成果につながる理由
プロは単なる内装デザインだけでなく、「どう働きたいか」という経営課題に基づいた設計を行います。業務フローや組織構造を反映したゾーニング、動線設計は専門知識が不可欠です。
現場に即した提案ができることが、成果につながる大きな理由です。
よくある内製と外注のギャップ
自社でレイアウトを考える場合、見た目の美しさやコスト重視に偏りがちです。その結果、「使いにくい」「移転後の不満が多い」といった事態になりかねません。
プロに依頼することで、社員視点・経営視点・空間視点のバランスがとれたプランが実現します。
移転成功の鍵を握る“ヒアリング力”
プロによる支援で最も重要なのは、ヒアリング力です。
形式的な要望を鵜呑みにせず、潜在的な課題や希望を引き出すコミュニケーションが、満足度の高いオフィスづくりに直結します。
リスビーが支援する空間づくりの特徴

物件選定から伴走する「リ・プロローグ」
リスビーの特徴は、オフィス移転の“前段階”から並走する点にあります。物件選びの時点で動線・面積・将来の拡張性を見据えた提案を行い、あらゆるリスクを減らします。
複数案で納得感あるレイアウト提案
一案のみの押し付けではなく、複数案を比較検討できるプロセスにより、経営層と現場の合意形成がスムーズになります。選べる設計は、納得感を高め、移転後の不満を最小化します。
東京・大阪を中心に3,200社以上の実績
リスビーは10年以上の経験と3,200社を超える実績を有し、幅広い業種・業態のニーズに対応してきました。働き方改革に直結するオフィス移転も数多く手がけ、確かな支援体制を提供しています。
まとめ
オフィス移転は、働き方改革を現実のものにする絶好の機会です。ただの「引っ越し」ではなく、社員の満足度や業務効率、組織の未来に直結する空間づくりの戦略です。
フリーアドレスやコミュニケーション設計といった空間面の工夫は、改革を加速させる実践的な手段となります。移転を成功させるためには、プロの知見と丁寧なヒアリングが不可欠です。
リスビーでは、企画から物件選定、設計・施工までをワンストップで支援し、企業の理想の働き方実現をサポートしています。働きやすさと成果の両立を目指すなら、ぜひ一度ご相談ください。