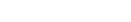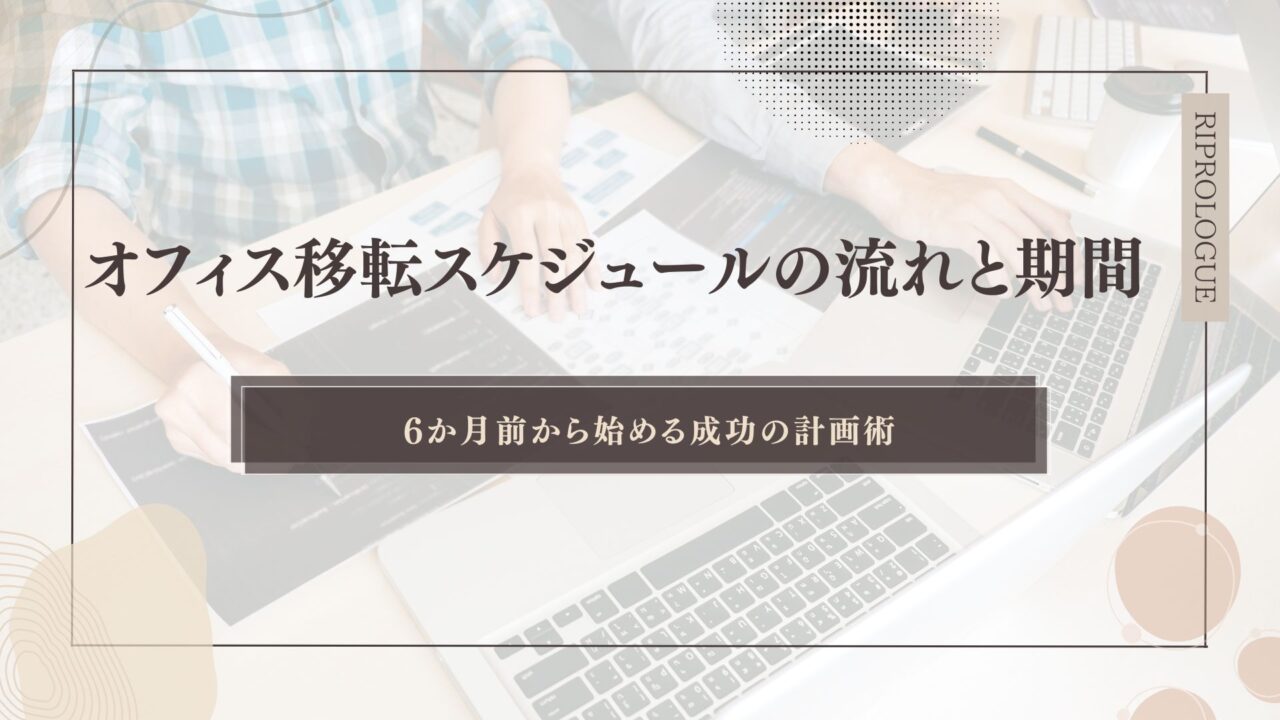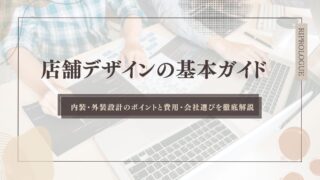オフィス移転は、物件選定や業者手配、各種手続きなど多くの工程が必要となる大きなプロジェクトです。スムーズに進めるには、6か月前からのスケジュール設計が欠かせません。本記事では、時系列で移転の流れを整理し、各フェーズのポイントや注意点を解説。業務への影響を抑え、成功に導くための実践的な移転計画を紹介します。

オフィス移転のスケジュールはなぜ重要か
オフィス移転は単なる「引っ越し」ではなく、企業の事業活動に大きな影響を与える経営上の重要プロジェクトです。特に、移転に伴う業務停止や混乱を防ぐには、明確なスケジュール設計と進行管理が不可欠です。
移転の各工程には、契約や工事、各種手続き、社内調整などの期限や条件が存在します。これらを場当たり的に進めると、業務が滞ったり、想定以上のコストが発生したりするリスクも高まります。逆に、計画的なスケジュールを立てることで、無駄な支出やトラブルを未然に防ぎ、限られた期間で最大限の成果を上げることが可能です。
スケジュール設計は、自社の業務規模や目的に応じて柔軟に対応することも大切です。小規模なオフィスであっても、関係業者の選定や契約、内装工事などには数ヶ月単位の余裕を持つ計画が求められます。
チェックリストでは見えにくい「時間軸」で考えるメリット
よく使われるチェックリスト形式は「何をやるか」は分かっても、「いつ、何をやるか」までの時期感が分かりづらいという課題があります。そのため、チェックリストと併せて、時系列のスケジュールに落とし込むことが非常に重要です。
また、スケジュール化することで、社内外の関係者と情報を共有しやすくなり、タスクの優先順位や進捗管理が明確になります。これは移転プロジェクト全体をスムーズに運営するための土台となります。
オフィス移転のチェックリストに関しては関連記事「オフィス移転をスムーズに!準備・工事・業務のチェックリスト完全ガイド」にて、各フロー別に詳細解説していますので、合わせてご閲覧下さい。
スケジュールの全体像|オフィス移転は6か月前から始まる
オフィス移転は一般的に、移転希望日の6か月前から準備を始めるのが理想とされています。移転プロジェクトは多くのステークホルダーが関与し、工程ごとの調整や確認に時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールが成功の鍵となります。
例えば、物件の選定や契約だけでも1~2か月を要することが多く、さらにレイアウト設計や内装工事、各種申請・届出などの準備期間も考慮しなければなりません。特に繁忙期(3月・9月など)は業者のスケジュールも埋まりやすいため、早期の着手が望まれます。
一般的なオフィス移転スケジュールの時系列(ステップ別)
以下は、一般的なオフィス移転のスケジュールを大まかに時系列で示した例です。
| 時期 | 主な作業内容 |
|---|---|
| 約6か月前 | 移転計画の立案、目的の明確化、移転先の条件整理、物件探し開始 |
| 約4~5か月前 | 物件内覧・選定、契約交渉、業者(PM・内装・引越し)選定 |
| 約3か月前 | レイアウト設計、内装・通信・設備工事の見積・発注 |
| 約2か月前 | 工事着手、関係官庁への届け出、移転案内の準備 |
| 約1か月前 | 備品手配、社内説明会、引っ越し準備の本格化 |
| 移転当日~直後 | 引っ越し作業、新オフィス稼働、原状回復工事・退去手続き |
※これは目安であり、自社の業務内容や規模に応じて調整が必要です。
自社に最適な期間を見極める判断基準
移転に必要な期間は、企業の事業規模・移転の目的・社内体制・決裁スピードなどによって異なります。たとえば、部署が複数に分かれている企業や、重要インフラの変更を伴う場合は、8か月以上かかるケースも珍しくありません。
逆に、同一ビル内でのフロア移動など小規模な移転であれば、3か月程度でも十分可能な場合もあります。ただし、たとえ小規模でも「契約」「届出」「工事」などの工程は発生するため、最短でも2か月程度の余裕は見ておきたいところです。
関連記事「オフィス移転の最適な時期はいつ?繁忙期とスケジュールを徹底解説」にて各シーズン別の特徴等、詳細解説していますので、合わせてご閲覧下さい。
フェーズ別|オフィス移転スケジュール詳細ガイド
6か月前〜:移転計画・目的の明確化と物件選定
オフィス移転の成功は、この最初のフェーズでいかに目的と方向性を明確にできるかに大きく左右されます。闇雲に物件を探すのではなく、まずは「なぜ移転するのか」「何を改善したいのか」を社内で共有し、移転の方針を固めることが重要です。
- 移転の目的・背景の明確化
例:事業拡大、賃料削減、老朽化、立地改善、働き方改革への対応など - 新オフィスに求める条件の整理
立地(駅近かどうか)、賃料、面積、レイアウトの自由度、ビルの管理状態など - 関係者(経営層・総務・IT・部門責任者)との意見共有
社内会議などで条件を集約し、合意形成を進める - 不動産会社への相談・物件情報の収集開始
移転希望時期、必要面積、現オフィスの解約可能日などを共有しながら物件探しを開始 - スケジュールの大枠を設定し、社内に周知
プロジェクトチームを立ち上げ、工程の大まかな目安を共有
4か月前〜:契約・業者選定とレイアウト設計
物件が決まり次第、次のステップとして進めるべきなのが、新オフィスの契約手続きと各業者の選定、そしてレイアウト設計の着手です。この段階での動きが、移転の全体スケジュールとコストに大きく影響します。
- 新オフィスの賃貸借契約の締結
契約日と入居可能日を明確にし、既存オフィスの解約と並行してスケジュールを調整します。
※通常、現オフィスは「解約予告○ヶ月前」の規定があるため要確認。 - 移転関連業者の選定と依頼
下記のような業者を選定し、相見積もりを取って契約を進めます。
- 内装工事会社
- オフィス家具・什器業者
- 引っ越し業者
- 回線・ネットワーク工事業者
- プロジェクトマネジメント(PM)会社(必要に応じて)
- 現オフィスの原状回復工事の内容確認
退去時に必要な原状回復の範囲をビル側と確認し、退去後の工事期間を把握しておくことが重要です。 - レイアウト設計・ゾーニングの開始
部門構成や社員数に合わせた席配置、会議室やリフレッシュスペースのゾーニングを計画。
設備や配線に関する条件もこの時点で把握し、後の工事に備えます。 - IT・通信インフラの要件整理
ネットワーク構成や電話・サーバー等の移設可否を確認し、ベンダーとの打ち合わせを開始。
2か月前〜:内装・設備工事、各種手続きの準備
新オフィスの契約や設計が決定したら、いよいよ実作業フェーズに入ります。この時期は、内装工事・通信設備の施工に加えて、官公庁への手続きや社内外への案内準備など、並行して進める作業が非常に多くなります。
- 内装・レイアウト工事の着工
設計図に基づいて内装工事を開始。オフィス家具の搬入日や、ネットワーク機器の設置タイミングと工程を調整しながら進めます。 - OA機器・IT機器・インフラ工事
サーバーやPBX、電話回線、インターネット回線など、ITインフラ周りの工事を並行して実施。
※回線の開通には数週間以上かかる場合もあるため、早めの申し込みが必要です。 - 各種行政手続きの準備
オフィス移転に伴い、以下のような官公庁への届出が発生します。
- 法務局:本店所在地の変更登記(必要な場合)
- 税務署:異動届、給与支払事務所等の開設届など
- 社会保険・労働保険関連:年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなど
※提出期限があるため、事前にリストアップし、順次対応します。 - 社外への移転案内の準備
取引先や関係会社へ送る案内状やメールの準備を開始。住所・電話番号・移転日などの情報を明確に伝えられるように整備します。 - 新オフィス用の備品・消耗品のリストアップと手配
文具や衛生用品、社名プレートや受付看板など、新たに必要となる備品類を洗い出し、発注しておきます。
1か月前〜:社内周知・備品移転の手配と工程確認
オフィス移転が目前に迫るこの時期は、社内体制の最終確認と現場での移転準備の具体化がメインとなります。日常業務と並行して行うため、混乱を防ぐための社内連携とタイムマネジメントが非常に重要です。
- 社員への正式アナウンスと説明会の実施
部署ごとの引っ越し手順や新オフィスでの注意点などを共有し、業務移行がスムーズに行えるよう準備します。フロアマップや座席表も配布すると安心感につながります。 - 引っ越しスケジュールの確定と工程確認
業者との最終調整を行い、搬出・搬入日時、立ち合いの責任者、搬入ルートの確認を済ませておきます。
特に土日や夜間作業を行う場合は、ビル管理会社への申請が必要なこともあるため注意が必要です。 - 現オフィスの片付けと不要品の廃棄計画
什器や備品の選別を行い、不要なものは廃棄、リユース、売却などで整理します。産業廃棄物の処分が必要な場合は、許可業者への依頼が必要です。 - 荷物の梱包と移転ラベルの配布
部署ごと・社員ごとの荷物を分類し、移転先でスムーズに展開できるようにラベルを作成。段ボールへの貼付を徹底します。 - 各業者との最終確認(家具・設備・回線等)
納品・設置日の再確認、工事の進捗確認、搬入物のチェックなどを行い、当日のミスを未然に防ぐ体制を整えます。
移転当日〜直後:引っ越し作業と入居後のチェック
いよいよオフィス移転の本番。このフェーズでは、これまでの準備が滞りなく実行されるかどうかが試されます。当日は予期せぬトラブルが起きやすいため、事前の確認と当日の現場管理が非常に重要です。移転後もすぐに通常業務を開始できるよう、立ち上げ時のチェック体制を整えておくことが求められます。
- 引っ越し当日の立ち合い・搬出入作業の監督
責任者を明確にし、各業者・社員と連携しながらスケジュール通りに作業を進めます。段ボールの搬入順や大型什器の設置位置など、現地で判断が求められる場面も多いため、指示系統は事前に整理しておきます。 - 新オフィス内の動作確認と動線チェック
ネットワークや電話、プリンターなど、業務に必要な設備が正しく稼働するかを移転直後に確認します。加えて、レイアウト通りに家具や什器が設置されているか、動線が確保されているかも現地で目視確認します。 - 社員向けの新オフィス案内とサポート体制の整備
初出社日にあたる営業開始日に混乱しないよう、案内資料の配布や総務・IT担当による現地サポート体制を用意します。コピー機や会議室の使い方、Wi-Fi接続方法などの**“ちょっとしたこと”の説明が、社員のストレスを減らす鍵**となります。 - 原状回復工事・旧オフィスの退去手続き
旧オフィスの明け渡しに向けた工事の進捗を確認し、引き渡し日までにすべて完了するよう工程を管理します。退去立ち合いや鍵の返却、精算書類の回収も忘れずに対応します。

オフィス移転スケジュールを成功させるためのポイント
オフィス移転をスムーズに進めるためには、単に工程を並べるだけでなく、社内外の調整・可視化・マネジメント体制の構築が不可欠です。ここでは、実行段階で移転プロジェクトを成功に導くための具体的なポイントを紹介します。
プロジェクト体制と社内リーダーの役割を明確にする
プロジェクトを進めるうえで、移転全体を統括する「推進リーダー」の存在が重要です。
そのうえで、以下のようにタスクを分担すると、対応漏れや属人化を防ぐことができます。
- 総務・管理部門:全体スケジュール管理、契約・届出、社内調整
- 情報システム部門:ITインフラの整備とベンダー対応
- 各部署の代表者:レイアウト確認、備品管理、社員対応
組織内での情報共有を強化するために、定例ミーティングやタスク一覧の進捗チェックも効果的です。
業者との連携を強化し、信頼関係を築く
内装工事、引っ越し、IT、原状回復など、複数の業者が関与するオフィス移転では、各社との連携ミスがスケジュール全体の遅延につながるリスクがあります。以下のような管理が有効です。
- 工程表(ガントチャート)の共有と進捗確認
- 施工・納品スケジュールの事前すり合わせ
- 問題発生時の連絡ルートと責任の明確化
業者との関係は「発注する側・される側」だけでなく、一つのチームとして連携する意識が大切です。
このように、スケジュールを立てるだけでなく、実行可能な状態に仕組み化しておくことが、最終的な成功に直結します。
オフィス移転を成功させるには、6か月以上前からのスケジュール設計と各フェーズごとの明確な作業計画が欠かせません。物件選定、業者手配、内装工事、手続き、社内調整までを時系列で整理し、可視化することが重要です。特に、業務への影響を最小限に抑えるためには、社内外の連携や情報共有、スケジュールの柔軟な見直しも求められます。限られた期間内で円滑に進めるためにも、プロジェクト体制の構築と進行管理の仕組み化が成功のカギとなります。