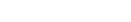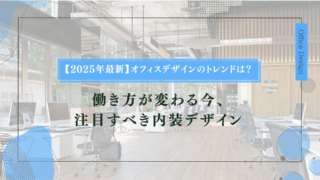- 「オフィス移転コンサルって料金がどれくらいかかるのかな…?」
- 「相場や内訳がわかりにくくて不安」
- 「成果報酬や固定報酬、どのプランを選べばいいんだろう」
そんな疑問を感じたことはありませんか?
本記事では、オフィス移転コンサルティングの料金相場や費用の内訳、料金体系ごとの違いを解説します。さらに、小規模から大規模オフィスまでのモデルケースや、部分依頼・フルサポートなど柔軟なプラン選びのポイントも紹介します。
これからオフィス移転を検討している企業の担当者や、費用感を把握して安心して判断したい方にぜひ読んでいただきたい内容です。

オフィス移転コンサルに料金が発生する理由

コンサルティングの役割と費用が発生する理由
オフィス移転のコンサルティングは、物件選定、レイアウト計画、工事見積の精査、進行管理、退去対応だけでなく、IT・通信環境の整備、セキュリティ要件への対応など、専門性の高い領域を含むケースも増えています。料金はこれらの幅広いタスクに割く工数と責任範囲に応じて発生します。社内だけでは拾いきれないリスク(工期遅延、原状回復漏れ、二重家賃など)を事前に防ぐ役割があり、この“判断の質向上”を投資と見なす企業が多いです。特に初回の移転では失敗が再起困難であり、料金を払ってでも「判断の質」を上げる投資と捉えます。
施工会社や不動産会社との違い
施工や仲介は自社の提供価値を前提に最適化されがちです。コンサルは特定の工法・商材に縛られず、複数案を比較し費用・相場・工期・品質を総合評価します。見積の抜け漏れや上振れ要因を第三者視点で是正し、発注スキームや契約条件のリスクを下げる点が差別化要因です。
なぜ料金体系がわかりにくいのか
移転規模、依頼範囲、契約形態が案件ごとに異なり、コンサル料金が定価化しづらいためです。さらに、成果報酬・固定報酬・月額といった料金体系の混在が理解を難しくします。本記事では「相場の目安」「費用の内訳」「プランの選び方」を明確化し、次章で数値レンジを示します。
オフィス規模別の移転コンサル料金相場
小規模オフィス(10〜30名)の相場
面積目安は30〜80坪。移転に関わる総費用として1,000万〜2,500万円程度とされるケースがあります。コンサル料金については明確な相場が公表されているわけではなく、案件ごとに変動します。ただし業界では、固定報酬で100万〜250万円程度、または総移転費用の3~10%程度を目安とすることが多いとされます。
中規模オフィス(50〜100名)の相場
100〜250坪程度で、総費用は3,000万〜7,000万円帯がめやす。コンサル料金はプロジェクト一括で300万〜700万円前後、もしくは5〜8%など割合課金が選ばれます。入居ビル規約が厳しい、セキュリティ要件が高いなど条件が増えるほど、工程・発注分割の設計に手間がかかり料金も上振れします。
大規模オフィス(100名以上)の相場
250坪超では利害関係者が増え、要件定義と調整コストが肥大化します。総費用は1億円を超えることも多く、コンサル料金は月額制×6〜12カ月や固定+成功報酬のハイブリッド設計が採用されることがあります。RFP策定、ベンダー競争、段階的移転などの高度な進行設計が料金体系を複雑化させます。
料金体系の違い(比較表)
| 料金体系 | 向いているケース | 課金基準 | 注意点 |
| 成果報酬型 | コスト削減余地が大きい | 削減額の〇% | 削減定義の取り決め必須 |
| 固定報酬(プロジェクト) | 範囲が明確 | 役務×期間×難易度 | 追加要件の精算条件を明確に |
| 月額固定 | 長期・大規模 | 月額×契約月数 | 目標とKPIの合意が前提 |
※数値は一例です。実際の相場は条件で変動します。次章でサービス内訳を見て、必要範囲を見極めましょう。

コンサル料金に含まれる主なサービス内容

物件選定サポート
立地・賃料・原状回復規約などを比較表に整理し、工事ルールや空調・電源容量などの隠れコストを洗い出して総費用に効く要素を明確化します。
レイアウト・設計のプランニング
席数・働き方を踏まえた複数プランを提示し、工事費・家具費を含む費用対効果の比較を行い、将来の増床余地や音環境・セキュリティ動線を考慮に入れます。
工事・施工の見積もり比較
同一条件で複数業者に見積を依頼し、項目単価・歩掛・仮設費の妥当性を検証。代替材や工程変更によるコスト削減案も提示します。
スケジュール管理と進行調整
クリティカルパスを管理しつつ、テナント工事申請・夜間工事・什器納品・ネットワーク導入・AV調整などを統括し、延長賃料などの費用影響を抑制します。
IT・通信環境の構築支援
ネットワーク・電話・PC設定、セキュリティ導入など、IT環境面の整備をサポートし、移転後すぐに業務が再開できる体制を整えます。
コスト削減のための交渉・調整
仮設・養生・搬入制限などの見積死角を特定して数量精査や相場との整合性を取ることで、料金透明性を担保します。
移転後の効果検証・フォローアップ
移転後のトラブル(什器不具合・動線のズレなど)対応や、従業員の満足度調査、改善の提案など、アフターサポートとして継続的な支援を行います。
料金を左右する3つの要因
オフィス規模と移転範囲
面積・人数・フロア分割の有無で費用とコンサル料金は大きく変わります。原状回復の厳格さや、夜間/休日工事の割合も相場を押し上げる典型要因です。
依頼するサービス範囲
物件選定〜発注〜竣工立会いまでをフルで依頼するか、見積精査と工程管理に絞るかで料金体系は倍近く変動します。プラン選びでムダを削れば、総費用の最適化が可能です。
契約形態(スポット依頼か継続契約か)
短期のスポットは成果が限定される一方、月額の継続契約はKPI連動で改善を積み上げやすい利点があります。自社の工期・体制に合わせ、相場だけでなく支払いの平準化も勘案しましょう。
モデルケースで見るオフィス移転のコンサル費用感
スタートアップ企業(想定) – 低コスト移転
50坪・20名想定。要件を絞り、居抜き活用と中古什器で費用圧縮したケースをモデル化すると、総費用:約1,200万円、コンサル料金:約140万円相当(固定報酬換算)。見積精査により電気工事仕様を合理化し、約120万円の削減が達成できる想定です。
中堅企業(想定) – 中規模移転
150坪・80名想定。会議室の遮音とセキュリティ要件強化を含めると、総費用:約4,800万円、コンサル料金:約5%(約240万円)と仮定できます。RFPによる競争入札、AV仕様の標準化で約350万円圧縮、ナイトシフト活用で二重家賃1カ月回避という想定です。
大企業(想定) – フルサポート型移転
400坪・250名想定。段階移転・ゾーニング・複数ベンダー調整を伴う複雑案件のモデルケースとして、総費用:約1.2億円、コンサル料金:月額制 × 9カ月(総額約900万円)を想定。相場以下での入札結果というケースを想定したモデルです。
※本事例はあくまで一つのモデルケースであり、実際の費用は規模・条件・支援範囲などにより大きく変わります。
コストを最適化する柔軟な依頼方法
部分依頼とフルサポート依頼の使い分け
要件が明確で社内PMが強いなら見積精査+契約交渉のみの部分依頼、未経験で判断に不安があるなら工程設計〜竣工立会いまでのフル依頼が有効です。コンサル料金を「必要な範囲」に限定し、総費用の最小化を狙います。
複数案から選ぶことでリスクを回避する
- レイアウト案A/B/C(投資額・工期・可変性)
- 仕様案スタンダード/ハイグレード(LCC視点で比較)
- 発注スキーム(分離発注/一括)
料金の妥当性は、相場比較だけでなく「代替案の相対評価」で担保されます。
初期相談を活用して見積もりを精査する
早期のヒアリングで費用のドライバーを確定し、RFPの粒度を揃えれば、見積差は大幅に縮まります。初期段階でプランの前提を整え、料金体系の取り決め(成果定義、増減精算)を明記することが、後半のトラブルと追加費用を防ぎます。
まとめ
本記事では、オフィス移転のコンサル料金を「相場の目安」「料金体系」「内訳サービス」「事例」「柔軟なプラン」の順に整理しました。重要なのは、費用の大小よりも意思決定の質と再現性です。自社の規模と体制に合うプランを選び、比較可能な複数案で料金の妥当性を担保しましょう。早期相談で前提を固め、RFPと契約条件を透明化すれば、相場に流されず合理的なコストに収まります。