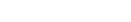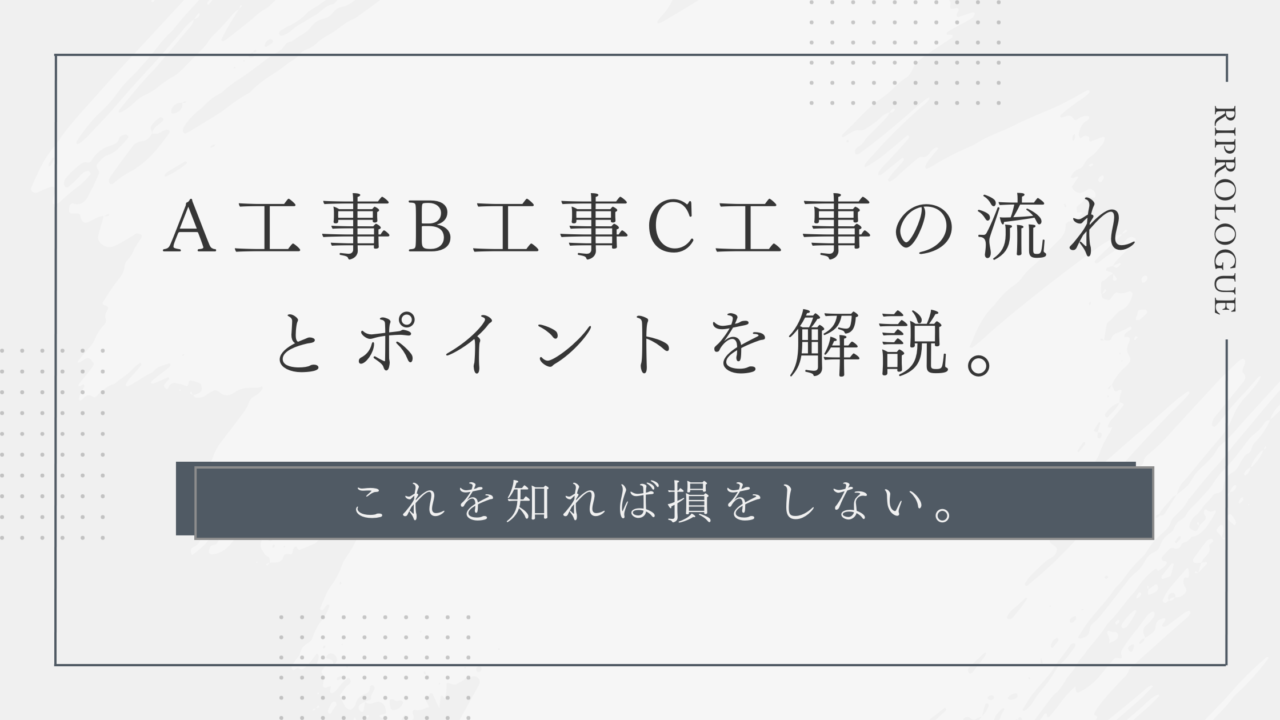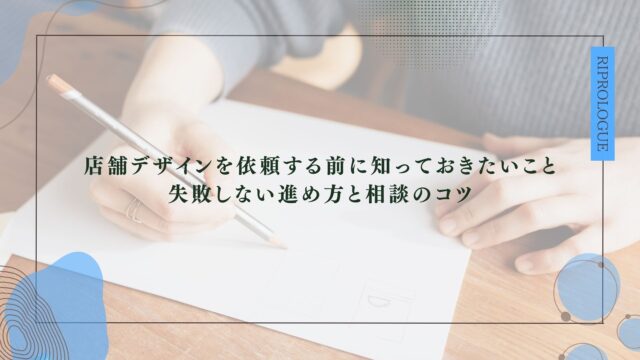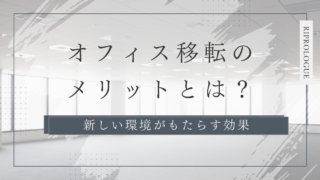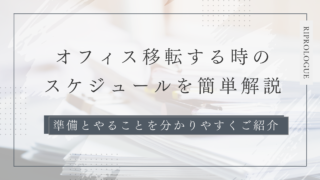「オフィス移転にあたってA工事・B工事・C工事の手続きや費用がわからず、トラブルになったらどうしよう……」
「ビル管理会社から工事区分の話をされたけど、具体的に何を注意すればいいの?」
こんなお悩みを解決します。
本記事を読むと得られる3つのこと
- 工事区分における発注・費用負担・業者指定のポイント
- A工事・B工事・C工事の違いと注意点
- 費用を抑えるためのコツや交渉術
本記事の信頼性
本記事を書いている筆者は、オフィス移転プロジェクトに数多く携わってきたプロフェッショナルです。これまでの経験から、移転時の工事トラブルや追加費用の事例を数多く見てきました。実際に施主・管理会社とのやり取りを行うなかで培ったノウハウを、わかりやすくご紹介します。
この記事を読み終える頃には、A工事・B工事・C工事への理解が深まるだけでなく、オフィス移転を円滑に進めるために必要な具体的な対策まで身につき、理想のオフィスを実現するための一歩が踏み出せるようになりますよ。ぜひ最後までご覧ください。

A工事・B工事・C工事の基礎知識
オフィス移転を検討するときは、単にデザインやレイアウトを決めるだけではなく、工事の内容や責任範囲についても整理しておくことが重要です。
特に、A工事・B工事・C工事という3つの区分を正しく理解していないと、追加費用や工期の延長、ビルオーナーとのトラブルなど、さまざまなリスクが発生しやすくなります。テナント側とビルオーナー側で工事区分を曖昧にして工事を始めた結果、契約不備から追加費用がかさんだり、完成後にやり直しが必要になったりする例も見受けられます。
そうしたリスクを最小限に抑えるためにも、それぞれの工事区分の特徴をしっかりと理解し、役割分担を明確にすることが欠かせません。ここでは、A工事・B工事・C工事の違いや、それぞれを区分する4つのポイントについて解説いたします。
工事区分とは(発注・費用負担・業者指定の基本情報)
オフィス移転やテナント工事を行う際、よく耳にする「A工事」「B工事」「C工事」という区分は、工事の発注者や費用負担者、工事会社の指定権限を明確にするための分類です。この分類は、建物の所有者(オーナー)と入居者(テナント)の役割や責任を整理し、スムーズな工事を進めるために重要な指標となります。
基本的な区分のポイントは以下の3つです:
発注者:誰が工事を依頼するのか。
費用負担者:工事費用を負担するのは誰か。
業者指定権限:どの業者が工事を担当するかを決めるのは誰か。
この3つの観点で明確に分けられるため、トラブルを防ぐだけでなく、各区分に応じた準備を適切に進めることができます。
A工事・B工事・C工事の違いと概要
以下の表にまとめたように、発注主体・費用負担・業者指定の有無が、それぞれの工事区分を判断する基本的な基準になります。どの区分にあたるかを明らかにすることで、工事に関する責任の所在や予算計画を明確にできるのがメリットです。
| 工事区分 | 発注者(主体) | 費用負担 | 業者指定の主体 | 主な対象工事 |
| A工事 | ビルオーナー | ビルオーナー | ビルオーナー | 建物全体の設備、基礎、共用部分 |
| B工事 | テナント | テナント | ビルオーナー | 防災設備、空調設備など |
| C工事 | テナント | テナント | テナント | テナント専有部分の内装、家具の設置など |
B工事C工事の流れを把握していないと起きるトラブル
オフィス移転において、B工事やC工事の調整が不十分なまま進めてしまうと、完成後のレイアウトや設備の使い勝手に大きな影響を及ぼす場合があります。
とくにB工事が終わった段階で問題点を見落としていると、C工事の段階になってから改修や設計変更が必要となり、時間も費用もかさんでしまいます。最終的にオフィス全体の完成度や快適性が損なわれるだけでなく、移転スケジュールそのものに遅れが生じるリスクも高まります。
B工事後の制約によるC工事への影響
B工事は空調や防災設備などの基本的な設備部分を整える重要な工程ですが、その計画が正確でなかったり、テナント側の希望する仕様を考慮しきれていなかったりすると、次工程であるC工事を予定どおりに進められなくなることがあります。
当初の計画で間仕切りの設置など予定していた場所に近接する形で、スプリンクラーや空調設備などが設置されていた場合など間仕切りの場所を変更しなければならないなどC工事に影響を及ぼす事が考えられます。
こうした影響は完成後のオフィスの快適性にも直結するため、B工事段階から最終レイアウトを見据えた調整が欠かせません。
追加費用の発生
B工事とC工事の連携不足による大きな懸念の一つが、追加費用です。
たとえば空調ダクトの位置が当初のレイアウトと合わず、空調設備の設置場所を変更せざるを得なくなるケースなどの問題が見つかると、B工事のやり直しや追加工事が必要になります。
その結果、工期が延びるだけでなく、施工範囲を広げる必要が出てくるため、通常よりも高額な費用が発生しやすくなります。
内装完成後の不具合
B工事とC工事の連携が甘いと、最終的なオフィスの使い勝手に影響が及びます。
とくに配線や空調の不備は、運用を始めてから初めて気づくことも多いため注意が必要です。たとえば、フリーアドレスエリアとして自由に席を移動できるよう設計したにもかかわらず、空調の噴出位置が偏っていて一部の席だけ温度が快適でない、あるいは電源コンセントの数が足りずにパソコンを自由に使いにくい、などの問題が挙げられます。
こうしたトラブルを防ぐためには、移転前の設計段階から実際の運用をイメージし、B工事・C工事それぞれの工程を見直すことが不可欠です。特にフリーアドレスのような新しい働き方を採用する場合は、必要な電源数やLAN配線、空調の範囲などを詳しく洗い出し、早期に施工業者やビル管理者と話し合っておくと良いでしょう。

費用を抑えるコツとコスト削減のポイント
事前に工事区分表を確認する
オフィス移転の際には、最初にA工事・B工事・C工事それぞれの内容をしっかり把握することが重要です。特にB工事やC工事はテナント側で費用を負担するケースが多いため、どの部分が自分たちの支払い範囲になるのかを明確にするだけでも、全体のコストを見落とすリスクを下げられます。
事前に工事区分表を確認しておくと、物件管理会社やビルオーナーと不要なトラブルを避けやすくなります。たとえば、仕切り壁の設置などB工事扱いになっていたにもかかわらず、後になって「C工事だと思っていた」という認識違いが発生すると、追加費用がかかってしまうことがあります。最初に区分表を確認し、誤解を防いだ企業では、追加予算計上の必要がなくスムーズに工事を進められたという声もあります。
あらかじめ誰がどの範囲を担当するかを正確に理解できれば、見積もり時のやりとりも効率的になります。細部の明確化によって無駄な支出を抑え、限られた予算内で計画を進められる可能性が高まります。
工事区分は物件ごとに異なる
同じような設備や内装工事でも、建物や物件によってA工事・B工事・C工事の扱いが変わることがあります。ですから、一つの事例をほかの物件にそのまま当てはめると、想定外の費用負担が生じる恐れがあります。
工事区分の違いは、建物構造やオーナーの管理方針、契約内容によるところが大きいです。B工事対象が多い物件ほど、実費負担額が増えやすい傾向があり、契約前の検討段階であらかじめ確認しておく必要があります。
ある企業では、「前の物件と同じ内装だから概算は同程度だろう」と予想していたところ、新しい建物でのB工事扱いが広範囲にわたったため、結果的に当初見込みより大幅なコスト増になったそうです。
以上の事から、各物件ごとに提供される工事区分表や契約書類を細かく読むことが大切です。オーナーや管理会社、仲介業者などに疑問点を確認し、必要があれば契約内容を再交渉するなど、建物特有のルールを踏まえた費用管理を行うことがコスト削減の近道になります。
B工事からA工事・C工事への変更交渉
特に注意が必要なのは、B工事が予想より高額になるケースです。B工事は、ビル指定業者が施工を行うため、相場よりも高めの見積もりになることがあります。そこで、場合によってはA工事やC工事に切り替えられないか、交渉を試みることも有効です。
一般的に、A工事は建物に直接関わる重要設備が対象となり、ビル側の負担や責任範囲が大きい工事です。一方、C工事はテナント側が業者を自由に選べるため、複数社から見積もりを取得して競合させやすく、費用を抑えられる可能性があります。ただし、建物全体の機能に影響する部分はC工事に変更できないこともあるため、交渉を進めるには専門の内装担当や管理会社との打ち合わせが欠かせません。
たとえば、防音工事で予想以上のB工事費用を提示された企業が「自社指定の内装会社でC工事にできないか」と管理会社に提案し、最終的に費用が半分以下に抑えられた実例があります。その一方で、物件オーナーの方針や契約書上の制限が厳しく、変更を認めてもらえないケースもあるため、事前に書類を詳細までチェックする必要があります。
結果的に、B工事が高額だと感じたら、スケジュールに余裕を持ったうえで「変更交渉の可能性」を探ってみることが、コスト圧縮につながる場合があります。
早めにC工事の業者へ見積依頼するメリット
C工事は、テナントが自由に業者を選べる工事です。
早期に業者を探し、見積依頼を進めることで、複数の提案や価格競争を期待できます。内装工事全体の予算を組む段階からC工事の費用を具体的に把握しておくと、B工事との差額やA工事での対応範囲などを検討しやすくなります。
また、オフィス移転の工程を早めに進めた企業ほど、工事スケジュールの遅延が少なく、追加費用が発生しにくくなります。早めに動くことで、複数業者にゆとりをもって見積もりを依頼できるため、スケジュール的にも費用的にも交渉しやすくなります。
最終的には、C工事の裁量権を活かすためにも、移転プロジェクトの初期段階で候補業者を探し、早めに見積もりやスケジュール感を共有しておくことがポイントです。
理想的なオフィス移転を実現するために
オフィス移転で最も大切なのは、A工事・B工事・C工事がスムーズに連携し、最終的に全工程を問題なく遂行する環境を整えることです。特にB工事やC工事が始まる前に、オフィス全体のレイアウトや必要な設備を踏まえたうえで、しっかりと計画を立てることが大切です。
というのも、B工事やC工事のやり直しは大きなコスト増だけでなく、移転スケジュールにも大きく影響を及ぼすからです。その結果、従業員が落ち着いて働ける環境を確保できなかったり、予想外の出費がかさんだりするなど、さまざまな問題が起こりやすくなります。
こうしたトラブルを防ぐためには、早めの段階で全体像を把握しながら、B工事・C工事の施工業者やオフィス移転をサポートする業者などと綿密に打ち合わせを行い、計画をしっかり固めておく必要があります。オフィス移転においても同様のリスクが考えられるため、計画初期から抜け漏れのない連携体制が必要です。
ここでは、B工事やC工事が円滑に進むために欠かせない具体的な取り組みとして、以下の3つのポイントを挙げます。複雑な工程が多いオフィス移転であっても、これらを着実に実行することで失敗を最小限に抑えられます。
業者選定
オフィス移転の工事では、B工事・C工事の区分ごとに別々の業者が関わることが多いです。しかし、それぞれの工事が単独で完結しないからこそ、全体を見渡せる業者やコンサルタントを選ぶことがカギになります。
B工事の空調や配線が適切に配置されていなければ、C工事で内装の美観や家具配置を理想どおりに仕上げるのは難しくなります。そのため、B工事・C工事を一貫してサポートできる体制を持った業者や、総合的な指示を出せるコンサルタントを選定することが非常に効果的です。
また、業者が見積段階から参画していれば、B工事段階で必要になりそうな設備仕様や、C工事で変化が生じそうな点についてあらかじめアドバイスを受けることができます。こうした事前準備があると、施工中に「この部分はやり直しです」といった事態を防ぎやすくなり、コストや手間を抑えられるでしょう。さらに、同じ業者がB工事C工事通じて対応可能であれば、部門間のコミュニケーションロスも減り、よりスムーズに作業が進行します。
業者との連携強化
B工事・C工事を担当する異なる業者同士が情報を共有し、互いの工程に合わせた作業計画を立てることが不可欠です。具体的には、B工事の施工内容をC工事の業者が十分に理解していないと、たとえば空調設備の吹き出し口の位置や配線ルートを微調整したいときに対応できないなどの問題が起こります。
こうした連携不足は、結果的に追加工事や設備の再調整を引き起こし、費用の増加やスケジュールの遅延につながります。B工事が終わった後で「ここは予定と違うため直さなければならない」といった事態を避けなければなりません。
そうすることによって、結果として、オフィス移転の最終的なゴールである「従業員が快適に働ける空間づくり」を効率よく進めることにつながります。
早期確認
B工事やC工事においては、レイアウト変更や設備増設といったイレギュラーが出やすいものです。もし移転直前や工事中に変更点が発覚すると、やり直し工事が発生して予定よりも大幅な費用がかかったり、引っ越しの日程がずれ込んでしまったりするおそれがあります。
そのため、できるだけ早い段階で図面や設備仕様、レイアウトイメージなどを具体的に確認し、疑問点や変更希望はその都度解消しておくことが大切です。そのような計画段階から業者をしっかり選び、常に連携を取りながら早期に問題点を洗い出しておくことで、B工事やC工事のやり直しや追加費用を最小限に抑えることができます。
こうした体制を整えたうえでオフィス移転に着手すれば、スケジュールに余裕を持った進行が可能となり、最終的に使いやすいレイアウトや快適な空調環境を実現することにつながるでしょう。
まとめ
オフィス移転でA工事・B工事・C工事を正しく理解しておくことは、不要なトラブルや追加費用を避けるうえで欠かせません。特にB工事とC工事の工程・制約を把握し、必要に応じてA工事への交渉や費用削減の工夫を行えば、全体のスケジュールを円滑に進められます。ここで、本記事の要点を振り返ります。
- 工事区分を事前確認
- 物件ごとの条件注視
- B工事後の制約警戒
- 業者連携で不具合回避
- 早めの見積依頼推奨
- 全体を見渡せる業者のサポートが重要
オフィスの移転の計画の早い段階で専門的な業者に相談することで、トラブルを回避でき、理想の環境作りを達成する近道となります。なかでも全体をトータルでサポートできる業者と連携することで、自社の負担を少なくし効率的に工程を進められる可能性が高くなります。
本記事を参考にすることで、複雑な工程を整理して、不要なやり直しやコストの発生を防ぎ、理想的な移転を実現しやすくなります。ぜひスムーズな移転計画を進めてください。