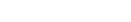オフィス移転を進める際、最初のつまずきが「計画の立て方がわからない」という悩みです。本記事では、実務担当者が押さえるべき移転計画の立案手順とスケジュール設計の考え方を解説します。あわせて、外注を活用することで得られる支援やメリットについても紹介します。

オフィス移転の成功は「計画準備」で決まる

なぜ事前の構想が移転の成果を左右するのか
オフィス移転は単なる「引っ越し」ではなく、企業の成長戦略や働き方改革の一環として捉えるべき重要なプロジェクトです。その成否は、ほぼ計画段階で決まるといっても過言ではありません。なぜなら、移転先で理想の働き方を実現できるかどうか、無駄なコストや業務停滞を避けられるかどうかは、準備段階の「意図設計」にかかっているからです。
戦略的にオフィスのあり方を考えることで、「単に狭いから移る」といった後追いの理由から脱却し、企業文化の可視化や採用力強化、生産性向上といった多面的な成果を引き寄せることが可能になります。
場当たり的な移転で起こるよくある失敗例
以下は、計画不足によってよく見られる失敗例です
- レイアウトが実情に合わず、使い勝手が悪化
- 必要な什器が納品遅れで業務スタートに支障
- 通信・インフラの切り替えが遅れてトラブル続出
- スタッフの声を反映せず、不満が増加
このような事態は、計画段階での検討不足や情報共有の遅れが原因となることが大半です。移転完了後に気づいても後戻りは難しく、結果的に多くのロスを生むことになります。
計画を始める前に確認したい3つの視点
移転の目的と達成したいゴール
オフィス移転を成功させるには、まず「なぜ移転するのか?」という目的を明確にすることが不可欠です。漠然と「手狭になったから」「更新時期だから」という理由では、移転先での設計やレイアウトに一貫性が持てず、長期的な価値を生みにくくなります。
以下のような観点で目的を整理しておきましょう
- 生産性の向上や働き方改革の推進
- 企業ブランディング・採用力の強化
- コスト最適化や業務効率化
- チーム間連携やコミュニケーションの改善
明確なゴールがあることで、移転計画の軸がぶれず、プロセス全体をスムーズに進行できます。
現オフィスの課題と改善したいポイント
移転によって「何を改善したいか」を具体的に洗い出すことも、計画設計には欠かせません。現状の不満や非効率を放置したまま移転しても、根本的な改善にはなりません。
以下の点をチェックしながら、移転後の改善イメージを描きましょう
- デスク間のスペースが狭い・動線が悪い
- 会議室や共有スペースの使い勝手が悪い
- 空調や照明、音環境に対する不満が多い
- 在宅・出社のハイブリッドに対応しきれていない
課題を明文化することで、移転の価値を社内に共有しやすくなり、社内稟議や外部業者とのやり取りも円滑になります。
移転に関わる関係者・体制の整理
オフィス移転は社内外の多くの関係者が関わるプロジェクトです。社内では経営層、総務、人事、情報システム部門が中心となり、業務影響の大きい部署からも代表者を立てて意見を集約すると効果的です。社外では不動産仲介、設計・施工、インフラ、引越し業者など多様なパートナーとの連携が求められます。
早い段階で関係者を整理し、役割や意思決定フローを明確にしておくことで、認識のズレや進行の遅れを防ぐことができます。情報共有や調整の手間を最小限に抑えるためにも、体制づくりは計画初期に必ず行いましょう。
オフィス移転計画の進め方ステップ
1.ヒアリングと現状把握
オフィス移転計画の第一歩は、現状の業務環境や組織課題のヒアリングから始まります。移転の目的が「業務効率の改善」「組織再編への対応」「働き方改革」など様々であるように、それぞれの課題や要望を部門ごとに把握することが重要です。トップダウンの方針だけでなく、現場の声を反映することで、納得感のある計画づくりにつながります。
- 経営層・現場双方からのヒアリングを実施
- 現オフィスでの不満や不便さを一覧化
- 今後の組織編成や事業展開も踏まえて現状を評価
2.移転に伴う対応項目の棚卸し
移転では多くの作業が並行して進行するため、初期段階で「何を」「いつまでに」対応すべきかを棚卸しする必要があります。これにより、抜け漏れの防止だけでなく、外注の要否判断やコスト見積もりの精度向上にもつながります。
- レイアウト設計や内装工事に関する要件整理
- インフラ整備(ネット回線・電話・電源等)の確認
- 書類変更や届け出、引越し作業の項目一覧作成
3.情報共有・稟議に必要な準備
計画段階では社内への情報共有と意思決定プロセスが重要になります。上層部の承認を得るためには、見積書や比較資料の整備が欠かせません。また、稟議通過後の社内浸透も見越して、関係者向けの説明資料を準備しておくとスムーズです。
4.社内外での調整の進め方
移転プロジェクトは関係者の数が多いため、調整の進め方が成否を分けます。社内では意思決定と実行部隊を分けて役割を明確にし、社外とは進捗管理表を用いた定例打ち合わせの仕組みを作ると、認識の齟齬や手戻りを防ぐことができます。

対応時期を見誤らないために知っておきたいこと
各工程にかかる作業量と検討タイミング
オフィス移転は、検討段階・実行段階のどちらにおいても「着手の遅れ」が後工程に大きな影響を与えます。とくに、内装設計やインフラ手配、什器選定は見た目以上に時間がかかる工程で、外部パートナーとの調整も発生するため、十分な準備期間を確保する必要があります。
- 内装設計や施工は最短でも1.5〜2ヶ月を想定
- 電話・ネット回線の手配は地域差もあるため早期相談が重要
- 家具や什器の納品リードタイムも事前に確認
判断が遅れると発生するリスクとは
意思決定の遅れは、全体進行に連鎖的な影響を及ぼします。たとえば、レイアウトの確定が遅れれば、内装工事も回線工事も待機状態になってしまいます。これにより追加費用や入居日延期といった事態も起こり得ます。スピード感をもった判断体制の構築が重要です。
- 工事や手配業務が後ろ倒しになり、費用がかさむ
- オフィス利用開始日に間に合わなくなる
- 社内業務や事業運営への影響拡大
柔軟な進行に必要な余白と段取り
タイトな進行では、予期せぬ変更やトラブルに対応しきれません。計画段階から「余白(バッファ)」を意識し、万が一の想定変更にも対応できる柔軟性を持たせましょう。各工程の前後に予備期間を設けておくことで、安心して移転準備を進められます。
専門家に依頼する理由と判断基準

計画段階から相談できる安心感
オフィス移転の初期段階では、「何から手をつけるべきか」が不明確なまま進めてしまうケースもあります。こうした場面で、専門家に早めに相談することで、目的の整理や必要なステップの可視化が可能になります。方向性を早期に定めることで、以降の判断もスムーズになります。
- 現状分析や目的設定から伴走してくれる
- 必要な工数や手配項目の整理が早期にできる
- 実現可能性を踏まえた移転計画が立てやすくなる
業者選定・設計・調整を一括で任せられる強み
複数の工程を自社内で管理するのは大きな負担です。移転支援を得意とするプロであれば、物件選定・設計・工事・什器の手配までを一貫して対応可能です。窓口を一本化することで、連絡・調整の手間が減り、社内担当者の負担軽減にもつながります。
- パートナー企業を探す手間が省ける
- 全体工程の遅延や抜け漏れを防げる
- 社内リソースを本来業務に集中できる
トラブル防止とコスト最適化への寄与
オフィス移転では、工事ミス・納期遅延・想定外の追加費用など、トラブルが発生しやすいものです。経験豊富な業者に任せることで、そうしたリスクを事前に回避し、コスト面でも過剰投資を防ぐ提案が受けられます。適正な範囲で最大限の効果を狙うことが可能になります。
どんな会社に依頼すべきかを見極めるコツ
単なる施工会社ではなく、「空間づくりのパートナー」として伴走してくれる企業を選ぶことがポイントです。企画・設計・施工すべてをワンストップで提供し、かつ複数案で柔軟な提案をしてくれる会社なら、課題や希望に応じた適切な移転計画を立てやすくなります。
外注するかどうかの判断基準とは
外注の判断は、社内のリソースと経験に応じて見極めましょう。自社で進行管理が難しい場合や、初めての移転でノウハウがない場合は、計画段階からのプロのサポートが非常に効果的です。「自分たちだけで進めるのが不安」と感じた時点で、相談を検討するのがベストです。
まとめ
オフィス移転は単なる「引越し」ではなく、組織の成長や働き方の改善につながる大きな転機です。だからこそ、やみくもに動き始めるのではなく、目的の明確化や体制の整備といった“計画準備”が成否を分ける重要なポイントとなります。
また、移転の進行には多くの調整や専門的な判断が求められるため、自社リソースだけで抱え込むのではなく、計画段階からプロに相談することでリスクを抑え、スムーズな実行につなげることができます。初めての移転でも安心して進めたい方は、ぜひ専門家への相談を検討してみてください。