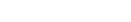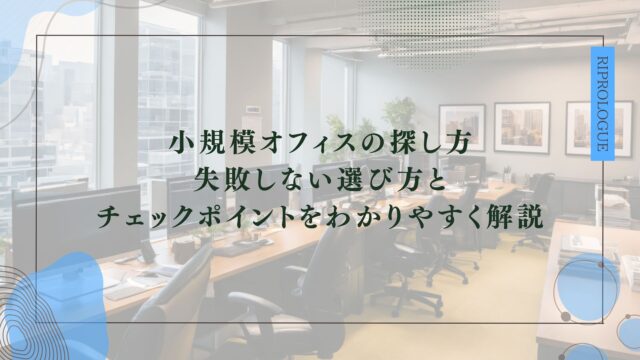オフィス移転の成否は「立地選び」で決まると言っても過言ではありません。通勤・コスト・企業イメージなど多くの要素が絡む中で、どのようにエリアを選ぶべきか悩むご担当者様も多いはず。
この記事では、立地判断の視点やエリア別の特性、企業成長に合わせた選び方を解説。プロへの相談で後悔のない移転を実現するためのヒントも紹介します。

なぜオフィス移転で「立地」が重要なのか

オフィスの立地は、単に「駅から近いか」「家賃が安いか」だけでは測れません。移転の目的や企業のステージによって、求められる条件は大きく異なります。
特に従業員の通勤利便性、顧客との接点、企業のブランディング、さらには災害リスクまで、幅広い要素が密接に関わってきます。立地選びの判断を誤ると、短期的なコスト削減は叶っても、中長期的には企業の成長を妨げるリスクにもなり得ます。
ここでは、立地が企業経営や組織運営にどのような影響を与えるのかを掘り下げて解説します。
立地選びが経営に与える影響とは
立地は企業の「見え方」と「働き方」に直結します。たとえば、オフィスが洗練された都市部にあることで、企業の信用度や採用力が高まるケースも少なくありません。
また、駅からの距離や周辺環境は、従業員の通勤満足度や定着率に影響を与える要素でもあります。さらに、顧客との商談や業務提携が頻繁に発生する業種では、訪問しやすい立地かどうかが重要です。つまり、立地は「人材・顧客・コスト」すべてに波及する経営資源であるといえるでしょう。
移転後に後悔する企業に共通する失敗例
オフィス移転後に後悔する企業には、ある共通点があります。以下のような判断ミスが多く見られます。
- 初期費用の安さだけを優先し、長期的な不便を招いた
- 通勤のしやすさを軽視し、離職者が増えた
- 商圏や取引先との距離を考慮せず、営業効率が低下した
- 将来の拡張や分室計画を見越さず、再移転コストが発生した
これらはすべて、「立地を単独の条件として」判断したことが原因です。立地選定は常に“全体設計の一部”として判断する必要があります。
立地選びを誤ると起こる3つのリスク
立地を適切に選ばなかった場合、以下のようなリスクが現実化します。
- 採用難・人材流出
通勤時間が長くなったり、周辺環境に魅力がない場合、既存社員の不満や新規採用のミスマッチを引き起こす要因となります。 - 顧客対応の低下
商談や訪問がしづらいエリアでは、クライアントとの関係維持が難しくなる場合があります。営業活動にも影響します。 - ブランドイメージの低下
オフィスビルや周辺の雰囲気が、企業イメージと一致しないことで、取引先や応募者に与える印象が悪くなるリスクもあります。
立地選びを誤れば、移転の本来の目的が台無しになってしまう可能性もあるため、戦略的な視点が欠かせません。
立地を決める際に押さえるべきポイント
オフィスの立地選定においては、ただ便利な場所を選べば良いわけではありません。目的に合った移転を実現するには、複数の観点からバランスよく検討する必要があります。
ここでは、移転時に見落とされがちなポイントを解説します。これらを意識することで、コストや満足度、企業価値にまで配慮した立地選びが可能になります。
通勤・交通アクセスの利便性
社員の通勤ストレスは離職や生産性低下の要因になります。そのため、立地選定では通勤のしやすさを最優先で考える企業も少なくありません。
- 最寄駅から徒歩圏内(5〜7分以内)が理想
- 複数路線が利用できる立地だと通勤リスクが分散できる
- バス、自転車通勤など複数手段への対応も重要
- 営業職が多い業種では外出のしやすさも加味する
特に郊外エリアに移転する場合は、既存社員の通勤手段の変化もシミュレーションしておくことが大切です。
周辺環境の利便性と安全性
働く環境は職場の快適性や満足度に直結します。以下のような観点から、周辺環境を評価しましょう。
- 飲食店やコンビニの充実度
- 医療施設、郵便局、銀行などの生活インフラ
- ビル周辺の治安や夜間の安全性
社員にとっては「通う場所」だけでなく「過ごす場所」でもあるため、単なるアクセスの良し悪しにとどまらず、総合的な環境の質で判断することが求められます。
エリアの賃料相場とコスト感
立地選びでは、コスト面の検討も欠かせません。ただし、単純な賃料の安さではなく、「費用対効果」を基準に判断することが重要です。賃料相場はエリアによって大きく異なるため、複数の候補地で比較するのが基本です。
また、共益費や更新料、原状回復費用なども含めて総額で検討する必要があります。初期費用を抑えても、長期的な不都合がコスト増につながるケースもあるため注意が必要です。
企業ブランディングとの整合性
企業の業種やターゲット層によっては、「どこにオフィスがあるか」がブランドイメージの形成に関わります。スタートアップ企業であれば渋谷、梅田などの先進エリア、コンサルや金融系であれば丸の内、淀屋橋などの高級感あるビジネス街といったように、立地そのものが対外的な信用力を示す役割を果たします。中小企業でも、清潔で統一感のある建物に入居することで、信頼感を与えることができます。企業の個性を立地でどう表現するかという視点は、採用や営業に直結する要素です。
災害リスクやインフラの安定性
災害への備えは、立地選定において見落とされがちな重要ポイントです。特に以下のようなリスク評価を行うことで、BCP(事業継続計画)の観点もカバーできます。
- ハザードマップによる浸水・地震リスクの確認
- 通信回線や電力インフラの強靭さ
- ビルの耐震基準や非常用電源の有無
災害時に拠点が機能しなくなると、取引先や社員への影響は甚大です。立地選定においては「もしも」の視点を持つことが信頼される組織への第一歩となります。

企業の規模別・立地判断の最適解
オフィスの立地選定は、企業の規模や成長フェーズに応じて「どの条件を重視すべきか」は変化するため、一律の基準では選べません。ここでは、創業期・拡大期・成熟期といったフェーズごとに、最適な立地判断のポイントを紹介します。
スタートアップ・小規模企業の場合
創業初期は限られたリソースを最大限に活かす必要があります。そのため、コスト効率と機動性を重視した立地選定がポイントとなります。
- 賃料が割安なエリアで、駅近の小規模物件を選ぶ
- 採用活動に有利なエリア(若年層が集まる地域)を選ぶ
- 将来的な移転を見越して、契約条件の柔軟性も確認
- シェアオフィスやサテライト拠点の活用も検討余地あり
このフェーズでは「成長の土台となる立地」であることが重要です。
拡大期・人員増加中の企業の場合
組織拡大フェーズでは、従業員の働きやすさやオフィスの拡張性が求められます。
- 複数路線が使える交通利便性の高い立地
- 延床面積の拡大に対応できるフロア構成かどうか
- 来客や面接が増えるため、アクセス性も重要
- 従業員属性に合わせた通勤圏分析を実施する
急激な組織拡大の流れに耐えうる、柔軟な立地選定が求められます。
成熟期・複数拠点を持つ企業の場合
成熟した企業では、立地の選定基準は「全体最適」の観点が重要となります。
- 複数拠点の役割を明確にし、バランスを保つ
- 本社機能はブランド性を重視して都心に、バックオフィスはコスト重視で郊外に配置
- 再編や移転の可能性を考慮し、交通アクセスや将来の移転性も検討する
都心エリア
都心部に位置する丸の内、大手町、梅田などは、日本を代表するビジネス街です。以下のような特長があります。
- 企業イメージや信頼性を高めたい場合に最適
- 大手企業・官公庁・金融機関との接点が多い
- 採用活動でブランド価値を高く見せられる
- 家賃は高めだが、投資対効果を重視する企業に向く
特に対外的な信頼性が問われる業種にとって、都心立地はブランディング戦略の一部となります。
周縁エリア
五反田、池袋、上野、本町などの周縁エリアは、コストと機能性のバランスが取れる選択肢です。立地としての主張は控えめでも、実用性が高い点が魅力です。
- 賃料を抑えつつ、駅近立地が見つかりやすい
- 渋谷や新宿へのアクセスも良好な場合が多い
- 中小・成長企業の移転先として人気
- 働きやすさと拡張性を両立したい企業におすすめ
特に「コストを意識しつつもアクセスは妥協できない」と考える企業にフィットするエリアです。
再開発エリア
品川、虎ノ門、中之島などの再開発エリアは、今後の成長性に期待が持てる立地です。
- 複数拠点の役割を明確にし、バランスを保つ
- 本社機能はブランド性や信用力を重視し都心に配置
- バックオフィス機能はコスト重視で郊外に配置
- 再編や移転性を考慮した交通アクセスの検討
コスト重視エリアの活用法
郊外や賃料水準が低いエリアは、コストパフォーマンスを重視する企業にとって有力な選択肢です。リモートワークやサテライト活用が進む中で、都心に固執せず「必要な機能だけを担保するオフィス戦略」も現実的になってきました。
地方拠点や分室として活用することで、本社機能と業務機能を分離し、柔軟な経営を実現できます。特に固定費削減と柔軟性を両立したい企業にとって、有力な立地選択肢です。
自社で判断できないときは?プロに任せる判断基準

オフィス移転は「立地選び」が最重要とわかっていても、実際には何を優先し、どのエリアを選べばよいか判断できずに迷う企業が多いのが実情です。
特に、候補地が複数あって絞り込めない場合や、移転の目的が曖昧な場合は、プロの力を借りることで確実な判断と選定が可能になります。ここでは、信頼できる支援パートナーの活用方法と、その判断基準を解説します。
専門パートナーが持つ“選定力”の違い
オフィス移転支援の専門パートナーは、単なる不動産情報を提供するだけでなく、企業の状況や目的に応じて立地の「選び方そのもの」を提案してくれます。
- エリア特性、賃料動向、将来の変化を含めて提案できる
- 採用・定着・ブランド戦略に基づいた判断が可能
- 企業フェーズや拡張計画も加味した中長期的視点を持つ
- 自社では得られない客観データに基づいたアドバイスが可能
特に「立地が正しかったかどうか」は移転後にしかわからないため、経験値のあるプロの意見を仰ぐことが後悔しない判断に直結します。
複数案による比較検討と将来設計の視点
立地判断を誤らないためには、選択肢を複数持ったうえで冷静に比較する視点が欠かせません。支援パートナーに依頼すれば、以下のようなアプローチが可能になります。
- 条件別に立地を絞り込み、比較表で評価できる
- 今後の人員計画や働き方改革を前提にした空間設計が可能
- コスト、アクセス、イメージなどの優先順位に基づいた比較提案
- 物件ごとの強み・弱みを整理した選定資料を提供してくれる
複数案を比較検討するプロセスは、「本当にこの立地でいいのか?」という不安を解消するうえで非常に有効です。
「物件選びから支援」できる伴走体制のメリット
実際に立地選定からオフィスデザイン・施工までを一括で任せられるパートナーは、移転担当者にとって非常に心強い存在です。
ヒアリングを通じて目的を整理した上で、移転後のレイアウト、ブランド表現、働き方の最適化まで視野に入れた提案が可能です。
株式会社リスビーのように、物件選定支援サービス「リ・プロローグ」を提供する企業では、移転初期からプロジェクト全体に伴走する体制が整っており、“点ではなく線”で空間づくりを考えられる強みがあります。
まとめ
オフィス移転における「立地の選定」は、企業の成長戦略や従業員の働きやすさ、さらにはブランドイメージにまで影響を与える重要な判断です。単なる通勤利便性や賃料の比較だけではなく、将来の事業展開や組織のフェーズに応じた視点を持つことが不可欠です。
本記事では、立地選びの基本的な視点から、企業規模別の考え方、エリア特性、そしてプロに任せる際の判断基準までを解説しました。もし「どこにすべきか」で悩んでいるなら、物件選定段階から伴走してくれる信頼できるパートナーの支援を検討してみてください。
株式会社リスビーでは、オフィス移転の企画・設計・施工までを一括対応。立地選びの段階から貴社の課題に寄り添い、理想の空間づくりをトータルでサポートします。移転をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。