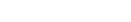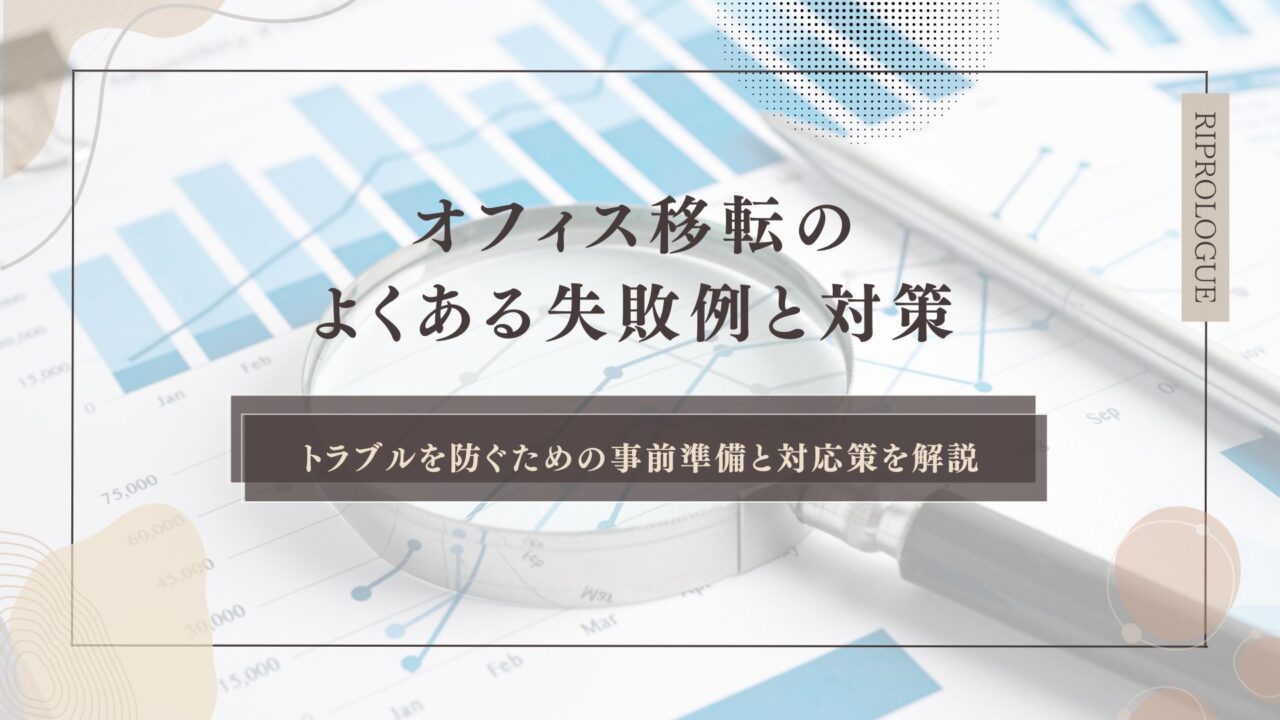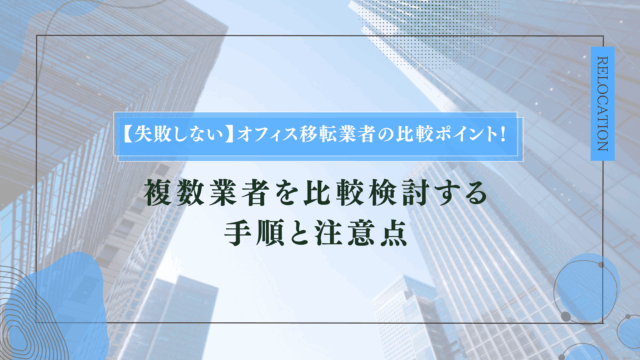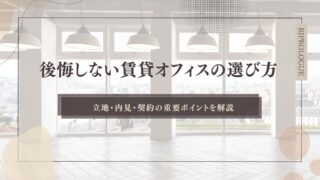オフィス移転は、物件探しやレイアウト設計、契約、引っ越し作業まで多くの工程が発生する複雑なプロジェクトです。その中で、スケジュールの遅延、費用の見積もりミス、社内調整不足など、さまざまな失敗が発生しやすいのも事実です。本記事では、実際に起きやすい失敗例をもとに、原因とその対策を具体的に解説します。事前にリスクを理解し、正しい準備と対応を行うことで、トラブルを未然に防ぎ、移転を成功へと導くヒントを提供します。

なぜオフィス移転では失敗が起こりやすいのか
プロジェクトの複雑性が引き起こすリスク
オフィス移転は単なる「引っ越し」ではなく、物件の選定からレイアウト設計、契約交渉、工事、各種申請、引越作業、社内周知まで幅広い工程と関係者が絡むプロジェクトです。その複雑さゆえに、経験がないまま進めてしまうと、思わぬ失敗に直面することがあります。
段取り不足・見積もり甘さが生む計画破綻
中でも特に多いのが、段取り不足によるスケジュールの遅延や、コストの過小見積もりによる予算オーバーです。また、現場を把握しきれていない状態で進めた結果、内装工事や設備に関する誤解・調整不足が起こるケースも珍しくありません。
社内調整の甘さと経験不足による判断ミス
さらに見落とされがちなのが、社内との情報共有や合意形成の不足による従業員の不満や混乱です。移転は環境の変化を伴うため、社員にとっては業務効率や通勤への影響、居心地といった点で敏感に感じる部分でもあります。
そもそもオフィス移転を経験する頻度は企業にとってそれほど多くはなく、担当者が移転のプロであることは稀です。そのため、各工程での判断や優先順位づけが曖昧になりやすく、業者任せにしてしまうケースも少なくありません。
こうした背景から、オフィス移転は失敗が起きやすい業務のひとつとされており、あらかじめ起こりがちなトラブルを想定し、対策を講じておくことが不可欠です。
上記を踏まえ、後述にて「よくあるオフィス移転の失敗例」を詳しく解説します。
よくあるオフィス移転の失敗例

オフィス移転においては、初歩的な見落としから重大なコストトラブルまで、実にさまざまな失敗が起こります。ここでは、現場でよく見られる失敗パターンを実例ベースで紹介します。
スケジュール遅延による業務混乱
移転日を決めたものの、内装工事や設備導入が間に合わず、移転後も一部のフロアが使えない、ネットワークが繋がらないといった事態が発生することがあります。その結果、社員の業務が滞り、クライアント対応にも影響が出るケースがあります。
原因としては、工事スケジュールの甘さや各工程のバッファ不足、業者との調整不備などが挙げられます。
予算オーバーと見積もりの甘さ
初期の見積もりでは収まりそうだった費用が、内装の追加工事やインフラ整備費の想定漏れで予算を大幅に超過することがあります。とくに、空調・電気・ネットワーク配線などの追加工事費は見落とされがちです。
また、オフィス家具や什器の買い替え、移転告知に伴う印刷・配送費なども後から積み上がる要因になります。
内装工事・設備に関する認識ズレ
レイアウト図面で決めた通りに施工されていなかった、または現場での寸法や配線条件を誤って把握し、予定していた設備が設置できなかったという事例もあります。
これは、設計者と施工者、クライアント側の意思疎通不足や現場確認の不足により起こります。
社内説明不足による従業員の不満
新オフィスに移転したものの、「席の配置が不便」「通勤時間が延びた」「空調や照明が不快」といった不満が噴出することもあります。
背景には、移転の目的やメリットが社員に十分伝わっていなかったり、レイアウトに現場の声が反映されていなかったりする問題があります。
オフィス移転を行うメリットに関しては「オフィス移転のメリットとは?新しい環境がもたらす効果」記事にて、コスト削減・結束力向上等、様々な視点から解説していますので、合わせてご閲覧下さい。
退去・契約条件を見落とした原状回復トラブル
旧オフィスの退去時に、想定以上の原状回復工事費を請求されるケースも多く見られます。
「契約書に記載された範囲を確認していなかった」「ビル指定の業者以外に頼めず高額だった」など、契約条件に対する認識不足が主な原因です。
リスビーは10年以上選ばれ続け累計施工実績3,200社以上!【全国対応】
オフィス移転の物件選びから、物件の立ち合い現地調査、そして設計・デザインまでワンストップで対応します。
- オフィスを拡大したいけど、どれくらいの広さが良いかわからない…
- オフィス移転から設計デザインまで費用が実際いくら必要なのか…
- フリーアクセスにしたい!個室が欲しい!各部署で要望が違う…どうすれば…
上記の様な悩みを抱える企業様は、是非、オフィス移転のプロに一度ご相談下さい。
リスビーでは「希望が全て叶う理想のオフィス移転の実現」をサポートさせて頂き「オフィス移転の失敗」を防ぐお手伝いをいたします。
まずは、お気軽にご相談(無料)下さい。
各失敗への具体的な対策と予防法
前のセクションで紹介した失敗は、どれも準備と対応次第で回避できるものばかりです。ここでは、具体的なトラブルに対して有効な対策方法を紹介します。
スケジュールの見える化とマイルストーン管理
移転までの全工程を一覧化し、いつ・誰が・何をするかを明確にしたスケジュール表を作成することが基本です。
月単位ではなく週単位、場合によっては日単位でマイルストーンを設定し、進捗管理ができるように可視化しましょう。
見積もり精査と追加費用のリスク対策
複数社からの相見積もりを取得し、内訳の比較と項目ごとの抜け漏れを丁寧に確認することが重要です。
「一式」と記載された費用は分解を依頼し、どの工程・作業が含まれているのかを明確化することで、後からの追加費用を抑えやすくなります。
内装・設備仕様のすり合わせ方法
図面上の打ち合わせだけでなく、現地での立ち会い確認を複数回行うことで、認識のズレを防ぐことができます。
設計担当者、施工業者、社内の関係部署が一堂に会してチェックを行う場を持つことで、情報共有がスムーズになります。
社内周知・巻き込み方と従業員ケア
移転の決定後は、社内向けに「移転の背景と目的」「メリット」「スケジュール」などを説明する場を設けることが効果的です。
レイアウトや座席配置についても、部署ごとの意見を吸い上げ、最終形に反映する姿勢が求められます。
契約内容と退去条件のチェックリスト
契約書を読む際は、原状回復の範囲、フリーレントの条件、途中解約時の制約、指定業者の有無などをチェックする必要があります。
分からない場合は、社外の専門家(PM業者や不動産コンサル)に同席してもらうのも一つの方法です。

オフィス移転を成功に導くための考え方
単なる作業ではなく「経営プロジェクト」として捉える
オフィス移転で失敗を避けるためには、チェックリストや手順に加えて、根本的な「考え方」や「進め方の姿勢」そのものが重要です。移転は単なる作業の積み重ねではなく、企業の今後を左右するプロジェクトと捉えるべきです。
目的を明確にし、判断軸をブレさせない
まず大切なのは、移転の目的を明確にすることです。
「賃料を下げたい」「手狭になった」「社員の働きやすさを改善したい」など、目的が曖昧なまま進めると、判断の軸がブレて不必要な費用や手間を招きます。どの目的を最優先にするのかを社内で共有し、すべての判断をその目的に紐づけるように意識しましょう。
感覚ではなく情報とデータで判断する
次に重要なのが、“感覚”ではなく“情報”で判断する姿勢です。
内装デザインの好みや立地の印象だけでなく、実際の運用コスト、設備仕様、社員の意見、業務への影響など、数値や具体的なデータに基づいて比較・検討することで、より合理的で後悔のない選択が可能になります。
関係者との連携とリスク対策が成功の鍵
また、成功する企業は社内外の「関係者との連携」を徹底しているという共通点があります。移転は多くの部署や外部業者が関わるため、情報伝達のタイミングや質が結果に直結します。意思決定を属人化させず、関係者全員が共通のゴールを持てるよう、小さな確認や共有を怠らないことがプロジェクト全体を安定させます。
そして、どれだけ準備していても想定外のトラブルは起こります。
その時に慌てずに対応できるよう、リスクを事前に洗い出し、代替案を用意しておくことがトラブル回避につながります。最悪のケースを想定しながら、最良の結果を目指すことが、移転成功の鍵となります。
オフィス移転の失敗によくある質問
移転先によって通勤時間が増えると、従業員のモチベーション低下や離職リスクの増加につながる可能性があります。とくに交通アクセスが複雑な場所や駅から遠い立地は不満の原因になりやすいため、移転前に従業員の居住エリアを把握し、通勤時間の変化をシミュレーションすることが重要です。
あります。特に事前の社内理解がないまま導入した場合、作業効率の低下や個人情報管理の甘さが問題になることがあります。部署によってはフリーアドレスが不向きな業務もあるため、部門ごとの業務スタイルを考慮した導入設計が必要です。段階的なテスト運用もおすすめです。
もちろんあります。予算や人手に余裕がない分、事前準備の抜けや社内連携不足によるミスが起きやすいのが中小企業の特徴です。例えば、部門ごとの役割が曖昧なまま進行し、必要な申請や備品手配が遅れるケースもあります。企業規模にかかわらず、明確なスケジュールと情報共有体制の整備が重要です。
オフィス移転を成功させるためには、段取りや知識よりもまず「失敗が起こり得る前提で準備する姿勢」が不可欠です。スケジュール、費用、社内外調整、契約条件など、どこか一つの油断がトラブルにつながります。だからこそ、移転の目的を明確にし、関係者全員と情報を共有しながら進めることが、失敗を防ぐ最大の対策です。思いつきではなく、計画的に。成功の鍵は、想定と対話にあります。