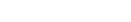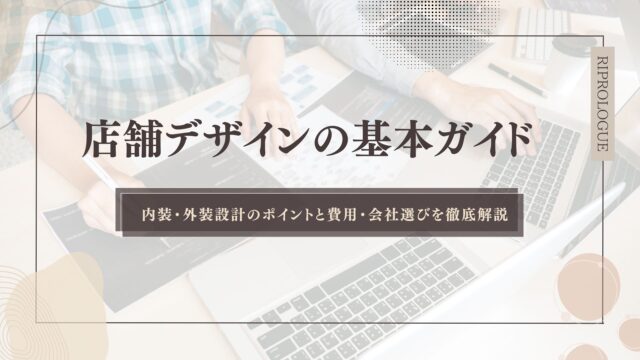多店舗展開は、事業の拡大やブランド力の強化に大きな可能性をもたらします。しかし、計画や実行において一歩間違えると、時間や資金を浪費し、大きな失敗につながるリスクも秘めています。多店舗展開に失敗する企業が直面する問題には、立地選定の誤りや資金繰りの悪化、人材不足、ブランド戦略の欠如など、さまざまな要因があります。これらの失敗要因を未然に防ぐためには、それぞれの課題を正確に把握し、適切な改善策を講じることが不可欠です。
本記事では、多店舗展開における「陥りやすい10の落とし穴」とその「回避策」を、具体的な事例とともに徹底解説します。また、成功を収めた事例をもとに、実践的なポイントやプロに依頼するメリットについても紹介します。多店舗展開を成功に導くための知識とヒントを学び、ぜひ貴社の成長戦略に役立ててください。

多店舗展開で陥りやすい10の落とし穴と失敗例
多店舗展開では、戦略的な準備と計画が不可欠ですが、特に市場調査や分析が不足していると大きな落とし穴に陥りやすくなります。この段階での失敗は、その後の展開にも深刻な影響を与えることが多いです。
綿密な市場調査・分析の不足
市場調査を軽視すると、出店先でのニーズを見誤り、競合と差別化できずに売上が伸び悩む原因となります。また、地域の購買力や人口動態を正しく把握しないまま進めることで、収益が計画に届かないことが多く見られます。
なぜ落とし穴になりやすいのか?
- ターゲット層とのミスマッチ
地域の顧客層を正しく分析しないと、提供する商品やサービスが求められず、来店客数が減少します。 - 競合状況の過小評価
競合店が多数存在するエリアで、価格や商品で差別化が不十分だと、集客に苦しむことになります。 - 商圏の過大評価
商圏の規模や購買力を過大に見積もると、収益性が低くなり、固定費の圧迫や赤字経営に繋がります。
失敗事例
ある飲食チェーンが、若者向けのカフェを地方都市に出店しました。しかし、市場調査が不十分だったため、ターゲットとしていた20~30代の人口が少ないことに気づかず、出店を決定。実際には高齢者が多い地域であったため、商品が受け入れられず、集客が思うように伸びませんでした。結果、半年で撤退を余儀なくされ、出店費用や運営費が無駄になってしまいました。この失敗は、地域の市場動向や顧客層のニーズを把握できていなかったことが原因です。
ずさんな立地選定
立地選定は多店舗展開の成功を左右する最も重要な要素の1つです。しかし、安易な判断や短期的な視点で立地を決めると、想定外の問題が発生し、売上や集客に深刻な影響を与えます。
なぜ落とし穴になりやすいのか?
- 集客力の低いエリアを選んでしまう
地域の人通りや交通の便を十分に調査せずに立地を選ぶと、顧客の流入が期待できず売上が低迷します。 - 家賃が高すぎる物件を選択
見た目の良さや一等地であることに惹かれて高額な物件を選ぶと、収益よりも固定費が上回り赤字に陥るケースがあります。 - 競合が多いエリアでの出店
競合店舗が多いにもかかわらず立地を選ぶことで、価格競争や集客面での課題が大きくなります。
失敗事例
ある企業が、駅前の一等地に新店舗を構えました。人通りは多かったものの、主な通行客層は通勤中のサラリーマンや学生で、商品ターゲットである主婦層がほとんどいないエリアでした。結果として、ターゲット層を集客できず、家賃負担が収益を圧迫。半年後には店舗を閉鎖する決断を迫られました。この失敗は、立地を表面的な条件だけで選んだことが原因です。
人材育成・マネジメントの甘さ
多店舗展開では、現場を任せる店長やスタッフの質が成功を大きく左右します。しかし、人材育成やマネジメントの不足が原因で、店舗運営がうまくいかずに失敗するケースが少なくありません。
なぜ落とし穴になりやすいのか?
- 店舗ごとの品質のバラつき
店長やスタッフのスキルが不足していると、サービスや商品提供の品質が店舗ごとに異なり、ブランドの信用が低下します。 - スタッフ不足や離職率の増加
教育体制が整っていない場合、スタッフが成長を感じられずモチベーションが低下します。その結果、離職率が上昇し、店舗運営に支障をきたします。 - 本部からのサポート不足
店舗運営を現場任せにしてしまうと、トラブルが発生した際に迅速な対応ができず、全体のパフォーマンスが低下します。
失敗事例
ある飲食チェーンが、多店舗展開にあたり短期間でスタッフを大量採用しました。しかし、研修期間を十分に設けなかったため、店舗ごとに接客品質や業務の効率に大きな差が生まれました。特にクレーム対応に不慣れなスタッフが顧客対応を誤ったことで、SNSで悪い評判が広まり、店舗全体の売上が急落しました。これは、適切な人材育成とマニュアルの整備が不十分だったことが原因です。
本部と店舗の連携不足
多店舗展開において、本部と各店舗がしっかりと連携できていないと、現場での混乱や運営の非効率が発生します。この問題が放置されると、全体のパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。
なぜ落とし穴になりやすいのか?
- 現場の状況を本部が把握できない
本部が店舗ごとの問題やニーズを理解していないと、適切なサポートが提供できず、現場での課題が解決されません。 - 方針や目標の共有不足
本部の方針が各店舗に浸透していない場合、現場での判断がバラバラになり、店舗間での運営に差が出てしまいます。 - コミュニケーションの欠如
店舗スタッフが本部に対して意見や提案をしにくい状況だと、店舗ごとの問題が解決されず、モチベーションの低下にもつながります。
失敗事例
ある小売チェーンでは、本部が各店舗への指示をメールで一斉送信していましたが、現場ではその指示が具体性に欠けていたため、解釈がバラバラになりました。例えば、陳列変更の指示が不明瞭だったため、店舗ごとに異なるレイアウトになり、顧客が混乱して商品を見つけにくい状況が発生しました。その結果、売上が低下し、本部が急いで修正指示を出すも、現場の不満が高まり、離職者が増える事態にまで発展しました。
個性のない店舗運営
多店舗展開では、効率化を目指してすべての店舗を同じ運営スタイルで管理しようとすることがあります。しかし、地域ごとの市場環境や顧客ニーズを無視した運営は、売上低迷や顧客離れを招くリスクを高めます。
なぜ落とし穴になりやすいのか?
- 地域ごとのニーズを無視
地域によって顧客の好みや購買行動は異なるため、一律のメニューやサービスが必ずしも効果的ではありません。特に地方と都市部では、顧客の購買力や生活スタイルが大きく異なります。 - 柔軟性の欠如
地域ごとに異なる課題や競合状況に対応できない運営スタイルは、店舗の成長を妨げます。現場スタッフの工夫やアイデアが活かされないと、従業員のモチベーション低下にもつながります。 - 差別化が難しくなる
他店との差別化を図るためには、地域特性に合わせた施策が必要です。画一的な運営では、競合に埋もれてしまい、顧客に選ばれる理由を作りにくくなります。
失敗事例
ある飲食チェーンが全国展開を進める際、全店舗で同じメニューと価格設定を採用しました。しかし、地方の店舗では価格が高すぎると感じられ、来店客数が減少。一方、都市部ではメニューのバリエーションが乏しいため、競合店に顧客を奪われました。こうした状況が長く続いた結果、地方の複数店舗を閉鎖する事態に陥りました。
過剰な初期投資と資金繰りの悪化
多店舗展開の初期段階では、設備投資や店舗開発の費用が大きく膨らむことがあります。しかし、無計画な初期投資や資金管理の甘さが原因で、運営に必要な資金が不足し、事業全体が停滞するリスクがあります。
なぜ落とし穴になりやすいのか?
- 過剰な設備投資
「集客力を高めたい」「他店舗との差別化を図りたい」といった目的で、高額なインテリアや設備を導入するケースがあります。しかし、回収可能な利益を見込んでいないまま進めると、経営を圧迫します。 - 資金繰りの計画不足
初期投資に多くの資金を割きすぎると、運転資金が不足し、急なコスト増に対応できなくなります。特に、想定より売上が伸びない場合、大きな損失につながります。 - 売上予測の誤り
楽観的な売上見込みに基づいて出店を進めると、収益が計画に届かず、結果的に資金繰りが悪化します。
失敗事例
あるアパレルブランドが、多店舗展開の一環として旗艦店をオープンしました。内装やディスプレイに莫大な費用をかけ、ターゲット層を意識した高級感のある店舗を完成させましたが、実際の売上は計画の半分以下にとどまりました。さらに、その資金不足を補うために借入金を増やした結果、利息負担が大きくなり、最終的には他の店舗の運営にも悪影響を及ぼしました。
ブランドイメージの毀損
多店舗展開を進める中で、ブランドイメージが損なわれることは致命的な問題です。消費者の信頼を失うと、個別の店舗だけでなく、ブランド全体の価値が低下し、売上や集客に大きな影響を与えます。
なぜ落とし穴になりやすいのか?
- サービスや商品品質のばらつき
店舗ごとに提供されるサービスや商品の品質が安定していないと、消費者に「ブランドとして信頼できない」と感じさせてしまいます。 - 急速な拡大による管理不足
短期間で多店舗を展開した結果、本部の管理が追いつかず、現場でのトラブルや品質低下が頻発します。 - 一貫性のないマーケティングやコンセプトのブレ
ブランドの核となるメッセージやデザインが店舗ごとに異なる場合、消費者に混乱を招き、ブランドの魅力が薄れてしまいます。
失敗事例
ある飲食チェーンが急速に多店舗展開を進めた際、店舗ごとにサービスのクオリティや料理の味にばらつきが生じました。顧客が「店舗によって満足度が異なる」という口コミをSNSで拡散したことで、ブランド全体の評価が急落。特に新規顧客が来店をためらうようになり、結果として売上の回復に時間がかかりました。
競合店の増加と市場の変化への対応不足
多店舗展開を進める中で、競合店の増加や市場環境の変化は避けられません。しかし、これらに適切に対応できない場合、顧客を奪われるだけでなく、ビジネス全体が衰退する危険性があります。
なぜ落とし穴になりやすいのか?
- 競合店の分析不足
新規出店や競合の強化されたマーケティング戦略に気づくのが遅れると、シェアを奪われるリスクが高まります。 - 市場ニーズの変化を見落とす
顧客の嗜好やライフスタイルの変化に気づかず、旧来のサービスや商品を提供し続けると、顧客の関心を引き続けることが難しくなります。 - 柔軟な戦略の欠如
急速な市場変化に対応するためのリソースや計画が不足している場合、競合店に先を越されてしまいます。
失敗事例
あるコンビニチェーンが、多店舗展開に成功したものの、新規参入した競合店が地域に根ざした商品ラインナップと低価格戦略を採用したことで顧客を奪われました。特に地域特化型の商品が求められていたにもかかわらず、全国共通の商品展開を続けた結果、消費者に「時代遅れ」との印象を与え、売上が大幅に低下。最終的には複数の店舗を閉鎖せざるを得ませんでした。
フランチャイズ展開における加盟店とのトラブル
フランチャイズ方式で多店舗展開を行う場合、加盟店との良好な関係を維持することが重要です。しかし、双方の信頼関係やルールが欠けていると、トラブルが発生しやすくなり、ブランド全体に悪影響を及ぼすことがあります。
なぜ落とし穴になりやすいのか?
- コミュニケーション不足
本部と加盟店間で十分な情報共有が行われないと、方針の違いや誤解が生じ、トラブルの原因となります。 - サポート体制の不備
本部が加盟店への運営サポートを怠ると、店舗の運営が滞り、顧客満足度や売上の低下を招きます。 - 契約内容の不透明さ
契約条件やロイヤルティの詳細が曖昧な場合、加盟店が不満を抱え、訴訟問題に発展するリスクがあります。
失敗事例
あるフランチャイズチェーンでは、本部が新規加盟店のオーナーに対して十分な運営指導を行わず、結果として加盟店の接客品質が低下しました。これにより顧客からのクレームが増加し、口コミサイトでの評判が悪化。さらに、加盟店オーナーとの関係が悪化して契約解消に至ったケースもありました。これらの問題は、本部の管理体制やサポート不足が引き金となったものです。
ITシステム導入・活用不足
多店舗展開を成功させる上で、ITシステムの導入と適切な活用は不可欠です。しかし、システム導入に対する意識が低い、または活用方法が不十分だと、店舗運営の効率が落ち、競争力の低下を招く可能性があります。
なぜ落とし穴になりやすいのか?
- 情報の一元管理ができない
ITシステムがない場合、在庫や売上データが店舗ごとにバラバラに管理され、全体の状況を正確に把握できません。 - 非効率な業務運営
アナログな手法を続けることで、スタッフの負担が増加し、ミスが発生しやすくなります。また、顧客データや売上分析を手動で行うと、迅速な意思決定が困難になります。 - 顧客満足度の低下
POSシステムや予約管理システムが整備されていないと、顧客対応に時間がかかり、不満を招くことがあります。特にデジタル化が進む現代では、システム対応が遅れること自体が競争力の低下につながります。
失敗事例
ある中規模チェーンでは、店舗間での在庫管理をエクセルで行っていたため、商品の過剰在庫や欠品が頻発しました。例えば、ある店舗では需要の高い商品が早々に売り切れた一方で、別の店舗では同商品が大量に売れ残るという事態に。これにより、全体の売上機会を損失し、無駄なコストが発生しました。この問題は、在庫管理システムの導入を後回しにしたことが原因です。
リスビーは日本全国を商圏に、10年以上選ばれ続け累計3,200社以上の施工実績!原状回復、コワーキングスペース、飲食、オフィス等、多岐に渡る実績を多数掲載しています。
「どんな店舗にしたいか、まだ具体的にイメージできない」と言う方は、是非ご閲覧下さい。
多店舗展開を成功に導くための主な回避策
多店舗展開で成功を収めるには、事前の準備と的確な運営計画が不可欠です。ここでは、よくある失敗を防ぐための主要な回避策を解説します。それぞれのポイントを押さえることで、リスクを最小限に抑えながら、長期的な成長を実現できるでしょう。
徹底的な市場調査と分析の実施
多店舗展開の第一歩は、ターゲット市場を深く理解することです。商圏内の人口動態、競合状況、顧客ニーズを徹底的に調査し、出店戦略を練ることが重要です。
成功のための具体的な取り組み
- 商圏分析ツールの活用
国勢調査データやエリアマーケティングツールを利用して、地域の人口構成や購買力を正確に把握します。 - 顧客ニーズのヒアリング
現地調査やアンケートを行い、地域の顧客が求める商品やサービスを明確にします。 - 競合店舗の徹底分析
競合店の強み・弱みを調べ、自社の差別化ポイントを明確にすることで、市場でのポジションを確立します。
最適な立地選定と商圏分析
立地選定は、多店舗展開の成否を大きく左右する重要な要素です。商圏の特性を把握し、地域のニーズに合った最適な立地を選ぶことで、集客力を最大化し、収益の安定を図ることが可能になります。
成功のための具体的な取り組み
- 商圏の詳細なデータ収集
- 人口動態、年齢層、購買力、通行量などのデータを収集し、出店候補地のポテンシャルを評価します。
- 周辺施設や交通アクセスの状況も確認し、顧客の来店しやすさを測ります。
- 立地特性に基づく出店判断
- 商業施設内か路面店か、繁華街か住宅街かなど、立地の特性に応じて出店形態を調整します。
- 地域ごとに異なる顧客層を考慮し、ニーズに合った立地を選定します。
- 競合の位置と影響を考慮
- 出店候補地周辺の競合店の状況を分析し、競争が激しいエリアを避けるか、自社の強みを活かして差別化を図ります。
注意点
- 見た目や利便性だけでなく、長期的な視点で収益性を判断することが重要です。
- 家賃や維持費が高すぎる物件は避け、安定した経営が可能なコスト構造を目指します。
計画的な人材育成と評価制度の構築
多店舗展開の成功には、現場で働くスタッフや店長の能力が大きく影響します。適切な人材育成と評価制度を整備することで、スタッフのモチベーションを高め、店舗全体の運営品質を向上させることが可能です。
成功のための具体的な取り組み
- 段階的な研修プログラムの導入
- 新人スタッフ向けの基礎研修から、店長候補向けのリーダーシップ研修まで、スキルアップを図るための段階的なプログラムを整備します。
- 実務に即したトレーニングを行い、現場で即戦力となる人材を育成します。
- 明確な評価制度の構築
- 業績や接客スキル、チームワークなどの要素を含む評価基準を設定し、スタッフの努力が正当に評価される仕組みを構築します。
- 優れたスタッフには報酬や昇進のチャンスを与え、モチベーションを高めます。
- マニュアルの整備と現場への落とし込み
- サービス標準や業務手順を網羅したマニュアルを作成し、全店舗で一貫した運営を実現します。
- マニュアルの内容が現場で実践されるように、定期的なフォローアップを行います。
注意点
- 人材育成は短期的な投資ではなく、長期的な視点で行うべきです。
- 評価制度が曖昧だと、スタッフのモチベーション低下につながるため、公平性を保つことが重要です。
多店舗展開を成功に導くための賢い選択 – プロに任せるという道
多店舗展開には、戦略立案、物件選定、店舗運営など、膨大なタスクが伴います。その全てを自力でこなそうとすると、時間と労力を浪費し、重要な部分に集中できなくなる可能性があります。そこで、多店舗展開の専門家や業者に任せる選択肢を活用することで、効率的かつ確実に事業を拡大することが可能です。
専門知識と豊富な経験による確実なサポート
プロフェッショナルは、これまでの実績や経験を基に、多店舗展開におけるリスクや課題を熟知しています。具体的には、以下のような点で支援を受けられます。
- 物件選定: 競合環境や商圏特性に基づき、適切な物件を紹介。候補物件の中から、収益性の高い立地を選ぶアドバイスを提供します。
- 事業計画の策定: 店舗展開スケジュールや必要な資金調達計画をプロが立案し、実現性の高い計画を作成します。
- 施工と店舗デザイン: 各地域の顧客層に合わせた店舗デザインの提案や、効率的な施工スケジュールの管理を一任できます。
時間とコストの最適化
多店舗展開では、スピード感とコスト管理が成功の鍵となります。プロに任せることで、以下のメリットが得られます。
- 短期間での出店: 自社で市場調査や物件交渉を行う場合、数ヶ月から数年かかることがあります。しかし、専門業者に依頼することで、これらのプロセスを大幅に短縮できます。
- コストの最小化: 経験豊富な業者は、予算内で最大限の効果を発揮する手法を熟知しています。物件交渉や施工コストの削減も期待できます。
リスクの可視化と回避策の提案
多店舗展開には多くのリスクが伴いますが、プロの支援を受けることで、潜在的なリスクを事前に特定し、適切な対策を講じることが可能です。
- 契約リスクの管理: 物件契約やフランチャイズ契約で発生するトラブルを未然に防ぐためのサポートを提供します。
- 地域特性への適応: 競合店の動向や市場変化を基に、店舗ごとに最適な戦略を提案します。
- オペレーション支援: 開店後の運営課題(人材不足、顧客対応のトラブルなど)にもフォローアップが受けられる体制を整えます。
経営者が本来の役割に集中できる
プロに業務を委託することで、経営者は本来の業務に集中できる環境が整います。特に次のような分野にリソースを集中することで、全体の事業成長を加速させることが可能です。
- 既存店舗の改善: 現状の課題解決に注力することで、顧客満足度の向上や収益改善を図る。
- 商品開発とブランド戦略: 新商品の開発やマーケティング施策に集中することで、競合との差別化を強化する。
- 長期的な事業計画: 店舗展開だけでなく、中長期的な成長戦略を立案するための時間が確保できる。
多店舗展開の全プロセスを自力でこなすのは、時間的・人的リソースに限界があります。専門業者の力を借りることで、リスクを抑えながら、着実に成功への道を進むことが可能になります。
多店舗展開の成功事例
地方都市での多店舗展開の成功
背景
ある飲食チェーンが、地方都市での多店舗展開を計画。地域特有のニーズを取り入れた戦略を立案し、プロフェッショナルのサポートを活用しました。
取り組み
- 地域密着型メニューの導入
- 地元の食材を活用した限定メニューを作成し、地元住民の支持を獲得しました。
- 商圏分析による立地選定
- 商圏分析ツールを活用し、家族連れが多いエリアや昼間の需要が高いエリアを優先的に選びました。
- スタッフ教育の強化
- 店長候補を事前に採用し、徹底した研修を実施。サービスの品質を全店舗で統一しました。
結果
- 地域の口コミで評判が広がり、オープン初月から目標売上を達成。1年以内に追加出店にも成功しました。
- 地域の住民から「地元に根ざしたブランド」として認知され、リピーターを確保。
フランチャイズ展開の成功
背景
ある中規模チェーンが、フランチャイズ方式での全国展開を目指しましたが、過去に加盟店とのトラブルが多発していたため、専門業者の協力を得て計画を練り直しました。
取り組み
- 契約内容の透明化
- 加盟店の利益を重視した契約条件を再設計。特にロイヤルティの計算基準を明確化しました。
- 加盟店オーナーとの関係強化
- 定期的なミーティングを開催し、本部とオーナー間のコミュニケーションを強化。現場の意見を積極的に取り入れました。
- 運営マニュアルの刷新
- 各店舗が統一されたサービスを提供できるよう、運営マニュアルを全面的に改定し、トラブルを未然に防ぎました。
結果
- 加盟店との信頼関係が構築され、新規オーナーの参入希望者が増加。短期間で10店舗のフランチャイズ展開を実現。
- 本部のサポート体制が充実し、加盟店の収益率が向上。全国的なブランドイメージの向上にも成功しました。
まとめ
多店舗展開は、事業拡大やブランド力の強化を実現する大きなチャンスである一方、計画の甘さや実行力の不足が大きな失敗につながるリスクを伴います。本記事で紹介した10の落とし穴、市場調査の不足や立地選定の失敗、人材育成やマネジメントの欠如などを理解し、それぞれの回避策を講じることが、成功への第一歩です。
さらに、成功を確実にするためには、専門知識と経験を持つプロフェッショナルの力を借りるのも賢明な選択です。信頼できるサポートを得ることで、時間やコストを効率化し、リスクを最小限に抑えながら事業を拡大できます。
最後に、成功事例からもわかるように、地域の特性や顧客ニーズに適応した柔軟な戦略が、多店舗展開の成功を導く鍵となります。リスクを正しく理解し、着実に前進することで、多店舗展開という目標を現実のものとしてください。